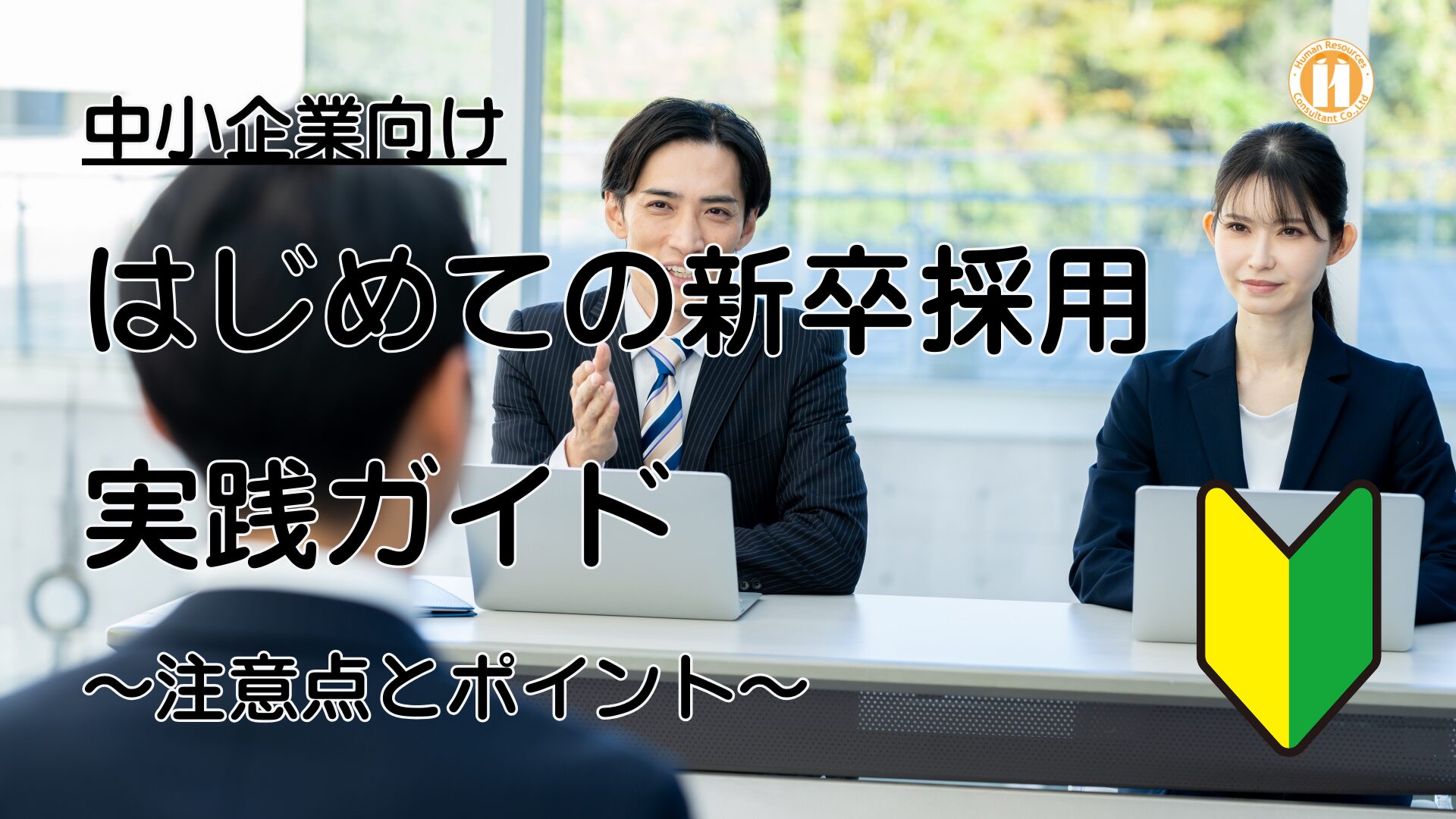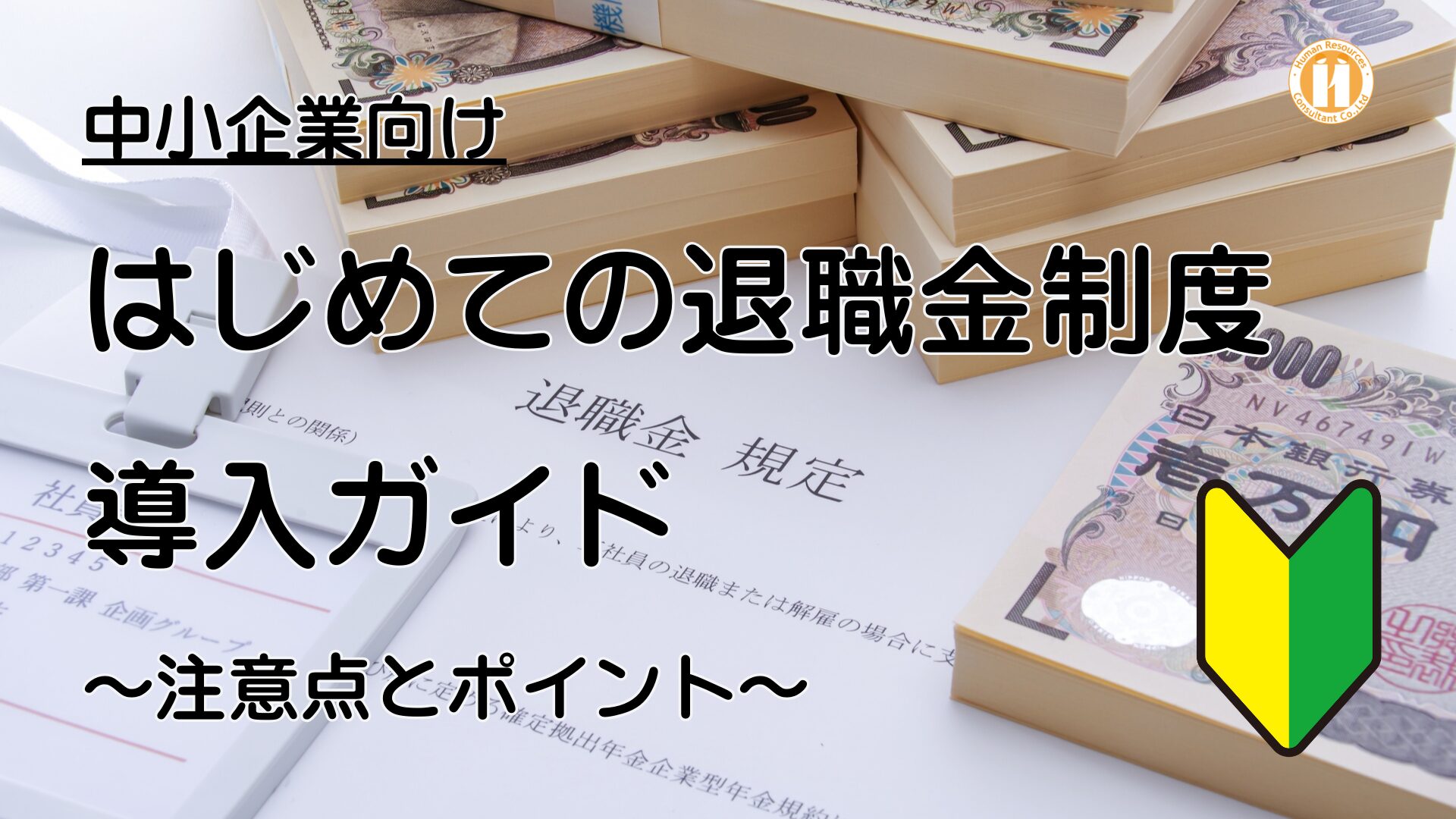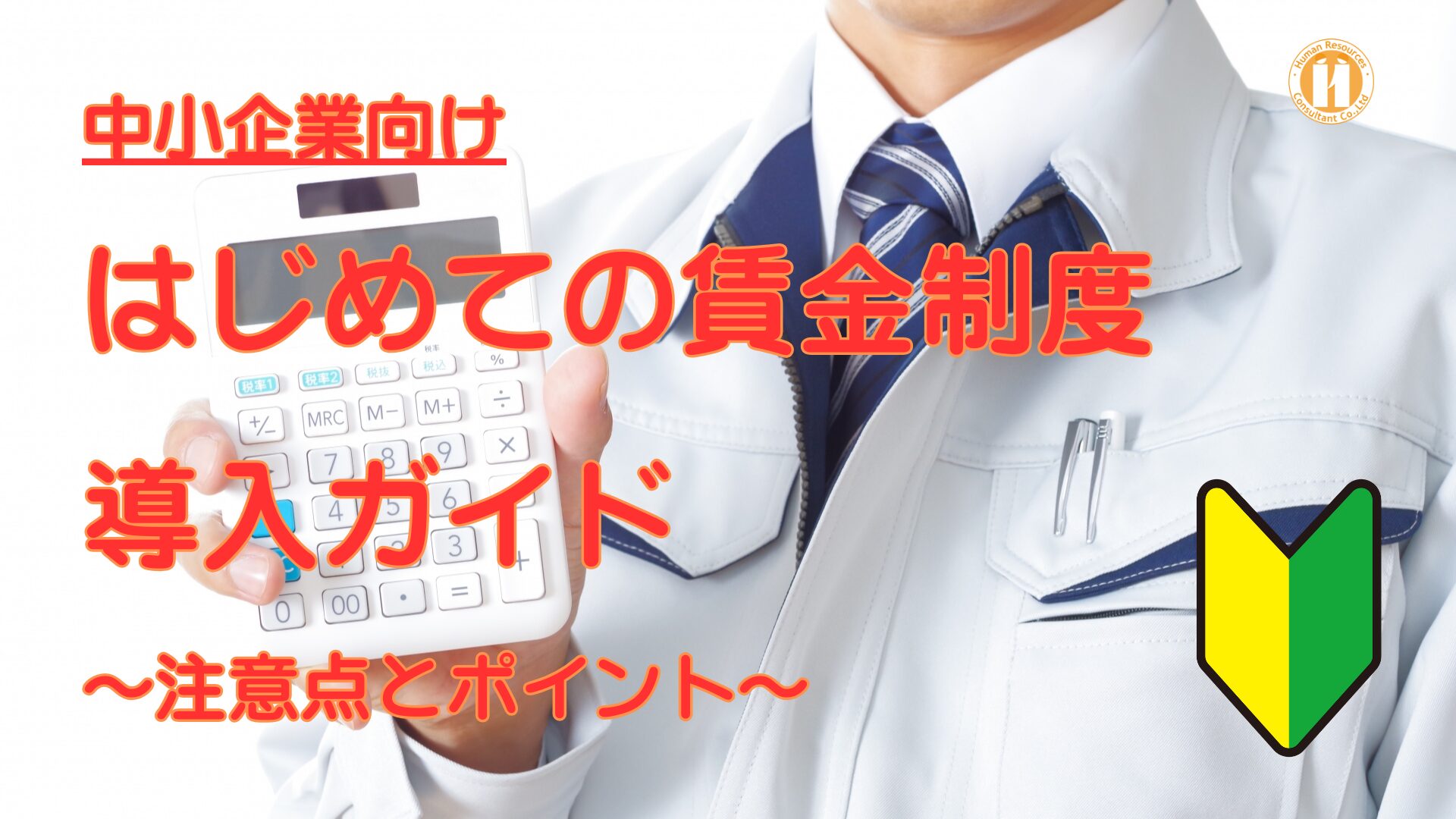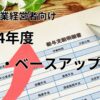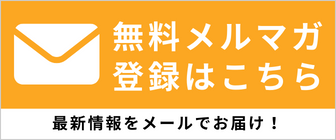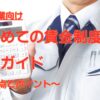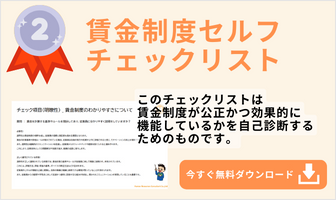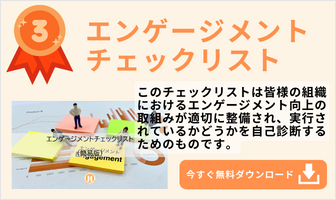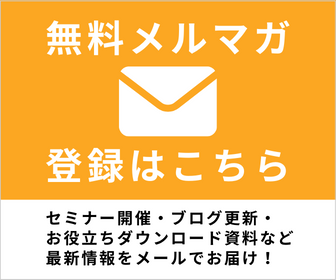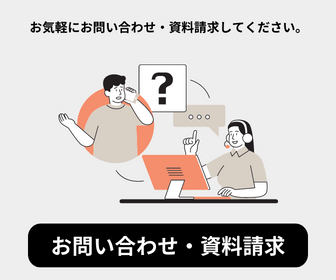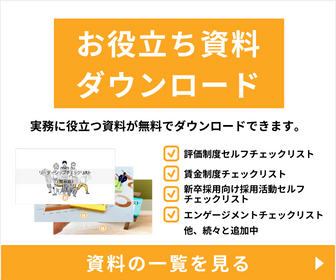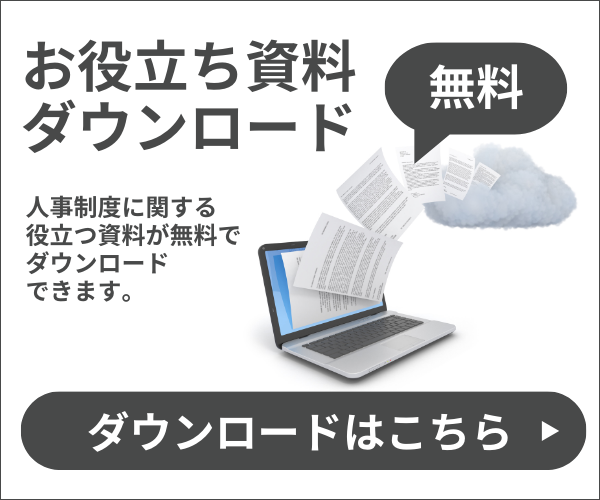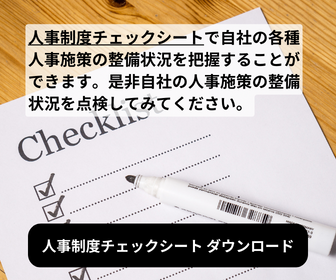中小企業向け | 2025年度春闘・ベースアップの見通し
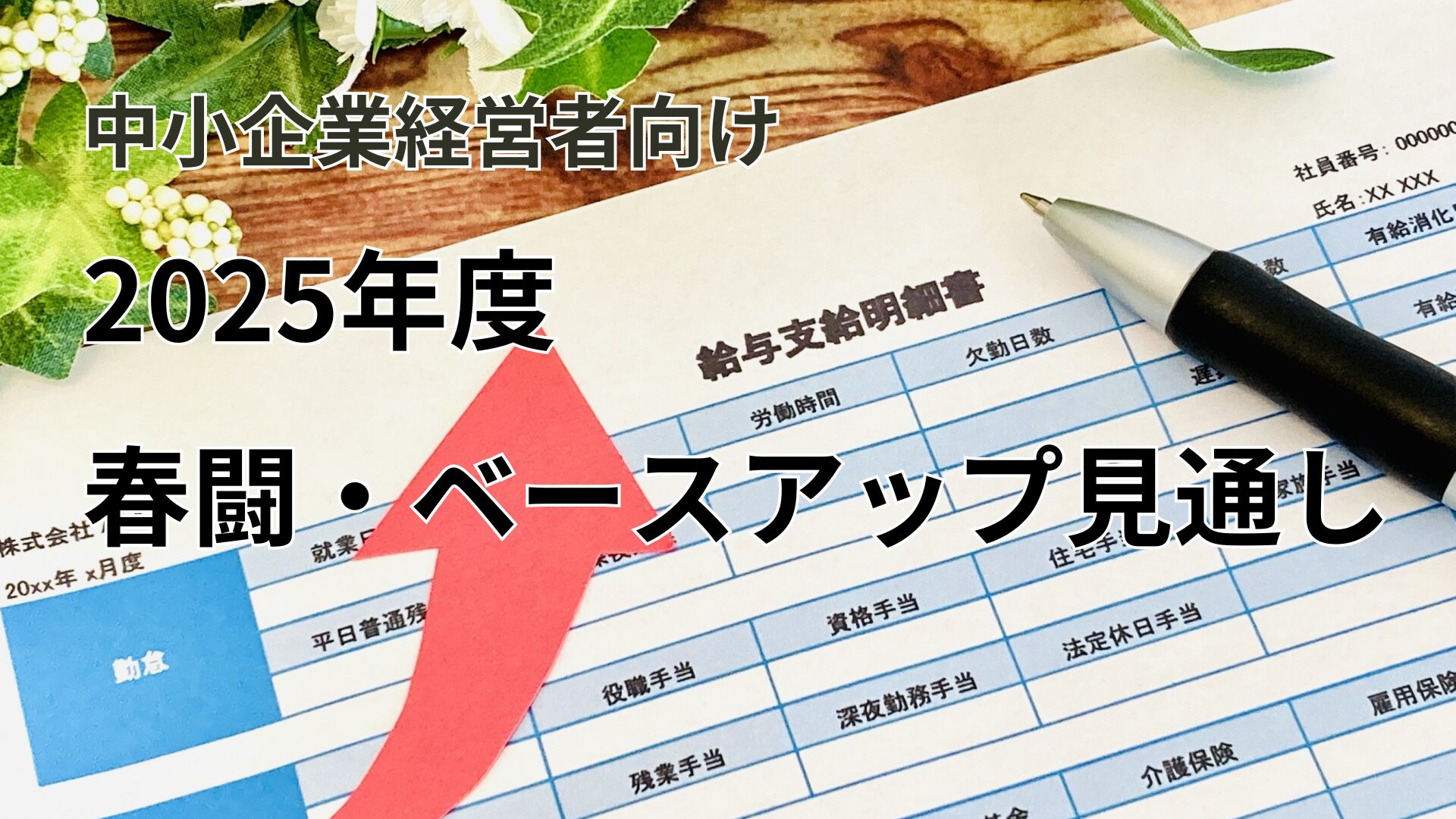
本コラムは、先にご紹介した2024年春闘の結果およびその背景を踏まえつつ、2025年の春闘やベースアップの見通し、そして中小企業の経営・人事戦略の視点を整理したものです。2024年のデータを参考にしているため、実際の数字や状況と多少の乖離が生じる可能性がありますが、今後の春闘の方向性を考えるうえでのヒントとしてお役立ていただければ幸いです。
はじめに
2024年の春闘において、大手企業の賃上げ率が約3.9%、中小企業が約2.8%となり、前年(2023年)並み、あるいはそれ以上の水準を維持したとされます(日本経団連・日本商工会議所公表データより)。コロナ禍からの回復基調やインバウンド需要の伸長、政府の賃上げ要請などが相まって、全体的に「高めの水準」が維持されました。しかし、物価高や原材料費の上昇が続き、業種によっては企業経営を圧迫する状況も残っています。
こうした環境下で迎える2025年の春闘は、さらに激しさを増す人材獲得競争や景気の先行き不透明感、国内外の金利や為替の影響など、さまざまな要素が絡み合うと予想されます。賃上げ率やベースアップの行方は、企業の経営戦略や人事制度の構築に大きく影響する重要テーマであるため、今から準備を進めることが望ましいでしょう。
2024年春闘を振り返る:大手企業と中小企業の差
2024年春闘の結果を受けて、大手企業と中小企業の賃上げ率が依然として開きがあることが再認識されました。大手企業ではおおむね3.9%前後の賃上げを実施し、高い水準を維持しました。海外市場での収益拡大やデジタル化による生産性向上などが背景にあり、物価上昇に対応したベースアップや高水準の賞与を提示した企業も少なくありません。
一方、中小企業は平均で2.8%程度の賃上げ率にとどまるという報告がありました。コロナ禍の影響から業績が完全には回復していない企業もあれば、円安による仕入れコスト高やエネルギー価格の高騰が経営を圧迫している企業も多いため、大手企業ほど積極的に給与改善を進められない実情があります。
こうした状況にもかかわらず、中小企業が従業員確保や離職率の低減に力を注がなければならないことは明白です。業種や地域によっては、深刻な人手不足が続いており、賃上げが不十分だと優秀な人材が他社に流れてしまうリスクもあります。政府が各種補助金・助成金を通じて賃上げを後押ししている面もあり、最低賃金の引き上げに合わせて賃金体系全体を再検討せざるを得ない企業が増えているのが現状です。
2025年春闘の見通し:高止まりか、さらなる上昇か
2025年の春闘では、以下のような要因が賃上げ率やベースアップの行方を左右すると考えられます。
- インフレと物価上昇の動向
2024年に続き、エネルギー価格や原材料費の上昇が続く場合、企業経営を圧迫する一方で、物価上昇に対応した賃金調整が求められると予想されます。特に従業員サイドでは「生活防衛」の観点から、ベースアップのさらなる引き上げを強く訴える可能性があります。 - 人材獲得競争の激化
大手企業だけでなく、ベンチャー企業やグローバル企業も含め、IT・AI関連の高度人材などをめぐる争奪戦が激しさを増しています。中小企業も独自の強みや魅力を打ち出しながら、人材確保のために給与・待遇の改善を検討せざるを得ない状況が続くでしょう。 - 政府・日銀の賃上げ要請と金融政策
日本銀行が金融緩和から徐々に方針を転換していくシナリオが取り沙汰される中、金利動向や円安・円高の振れ幅によって輸出入企業の業績やコスト構造が変動する可能性があります。また、政府も「経済の好循環」を目的とした賃上げ要請を続けるとみられ、中小企業に対して補助金や減税措置を拡充することが期待される一方、賃上げを実施できない企業への風当たりは厳しくなる可能性があります。 - 業種間・地域間の格差
観光や外食、サービス業などは需要回復が進むと予想される一方、世界経済の先行き不透明により外需が減退する業種も出てくるかもしれません。地域によってはインバウンドや大規模イベントの誘致に成功している一方で、地元需要が伸び悩む場所もあり、業績格差がさらに拡大することが考えられます。その結果、賃上げ率も企業規模だけでなく、業種・地域ごとに大きな差がつくことが予想されます。

2025年ベースアップの注目ポイント
ベースアップは長期的に従業員の給与水準を底上げするものであり、春闘において特に注目されるテーマです。2025年には、以下のようなポイントが焦点となるでしょう。
- 業績連動型賃上げの加速
ベースアップと定期昇給の区別が曖昧になりつつある企業も増えていますが、企業ごとに「業績連動型」の賃上げを導入し、成果が出た年度にはベースアップ率を上乗せするといった制度設計を考える動きが広がる可能性があります。 - 最低賃金引き上げとの関係
ここ数年、最低賃金は毎年引き上げが行われており、2025年もその傾向が続く見通しです。最低賃金が上がると、企業はアルバイト・パートから正社員まで含めた賃金テーブル全体を見直さざるを得なくなるケースが多いため、ベースアップ率の引き上げ要請が一層強まることも考えられます。 - 人材投資とエンゲージメント向上
賃金を上げるだけでなく、研修制度やキャリアアップ支援など「人材投資」を重視する企業が増えています。従業員自身が成長実感を得られる環境を整えることで、中長期的に生産性を高め、企業の競争力向上につなげる狙いがあります。ベースアップと人材育成をセットで進める施策は、若手人材や専門人材にとって魅力的に映るでしょう。
中小企業が注目すべき対策とポイント
2025年の春闘に向けて、中小企業が今から取り組むべき対策やポイントを以下にまとめます。
生産性向上とDXの推進
ベースアップや人材確保には「資金的な余裕」が欠かせません。国や自治体の補助金・助成金を活用しつつ、業務プロセスの見直しやデジタルツールの導入を進めて生産性を向上させることで、賃上げの原資を確保することが重要です。
メリハリある賃金制度の整備
全員一律のベースアップだけでなく、職種や成果に応じてメリハリをつけた人事制度を検討する企業が増えています。特に専門人材やリーダー人材の獲得・定着を狙う場合は、これらの従業員に対して積極的な賃上げやインセンティブを設定することが有効です。
働き方改革や企業文化の再構築
コロナ禍を経て、リモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を導入する企業が増えました。給与だけでなく「働きやすさ」や「企業カルチャー」も重要な要素となり、従業員満足を高めることが結果的に企業の競争力につながります。職場環境を整え、従業員が自律的に働ける仕組みを築くことで、中長期的に定着率を高めることができるでしょう。
段階的・計画的なベースアップ戦略
一度に大幅なベースアップが難しくても、数年かけて段階的に引き上げていくプランを示すことで、従業員に安心感とモチベーションを与えることができます。また、年度ごとの業績や目標達成度に応じて、ベースアップ率を柔軟に調整する仕組みを取り入れるのも選択肢の一つです。
まとめ:2025年に向けた春闘・ベースアップの展望
2025年の春闘は、2024年同様に大手企業と中小企業の賃上げ率やベースアップで差が生じることが予想されます。人手不足、物価上昇、業績格差といった要因が複雑に絡み合うなか、政府は引き続き企業に対して賃上げを強く促し、日銀も金融政策を含む経済環境の変化を注視していくでしょう。
中小企業の経営者や人事担当者の皆様には、単に賃金を上げるだけでなく、生産性向上や人材育成とセットで検討する「総合的な経営・人事戦略」の重要性が増していると言えます。ベースアップのための原資をどのように確保し、従業員にどんな価値を提供できるかが、企業の将来を左右する大きなポイントです。
2024年の春闘で示された約3.9%(大手)と2.8%(中小企業)の賃上げ水準は、2025年においても一つの目安となるでしょう。しかし、世界経済の動きや国内の金利・為替動向、業種・地域ごとの需要格差、さらには人材獲得競争の激化など、不確定要素は依然多く存在します。こうした変化に柔軟に対応しながら、従業員一人ひとりが成長し、企業が持続的に発展できる仕組みを整えることこそ、これからの経営者・人事担当者に求められる使命と言えます。
最後に、2025年の春闘とベースアップが企業と従業員双方にとって実りあるものとなるよう、早めの情報収集と戦略的な準備を進めていただければ幸いです。前向きな労使交渉と互いの理解・協力のもとで、生産性向上・給与改善・企業価値向上の好循環を築き上げていきましょう。
投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。