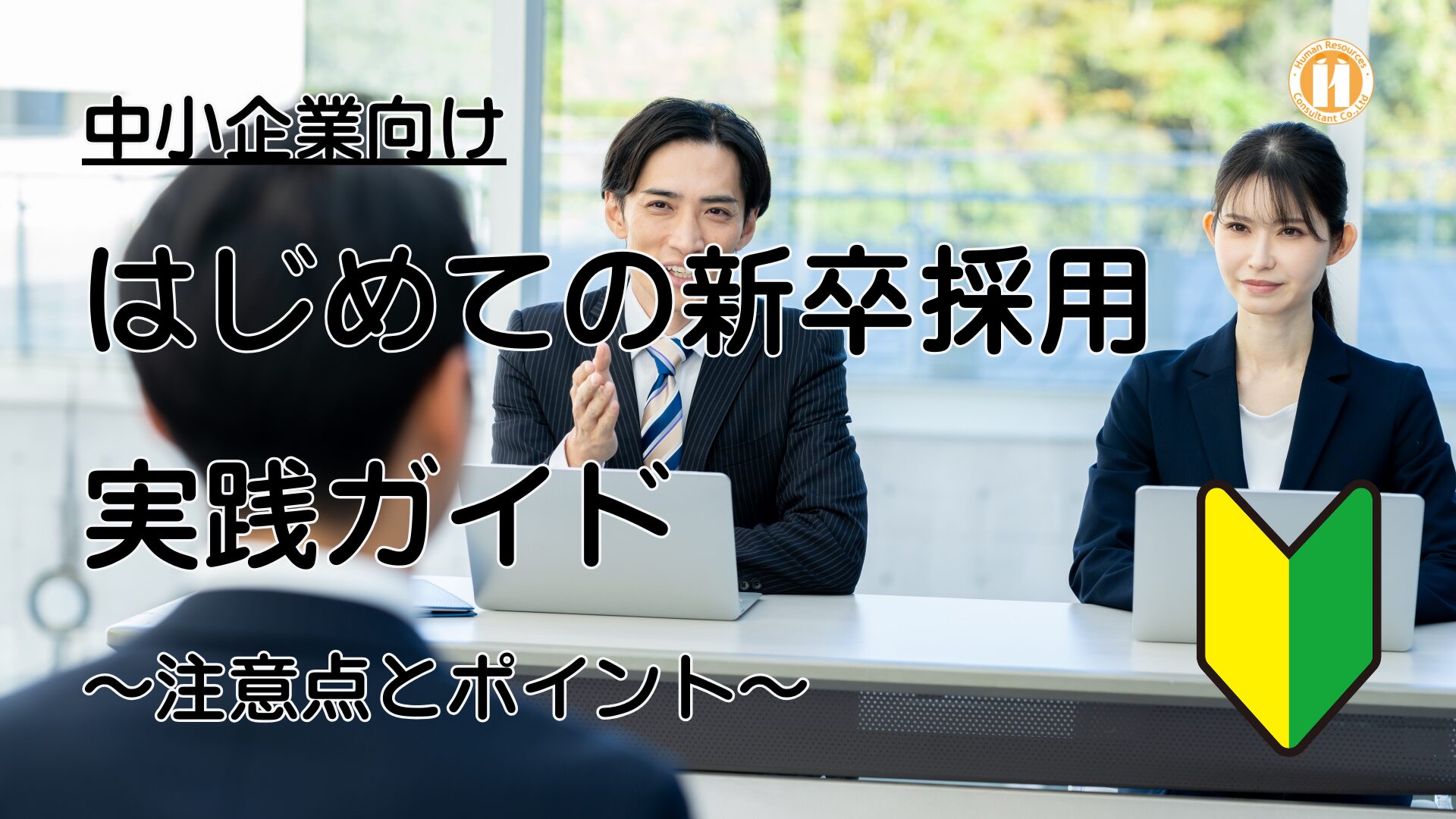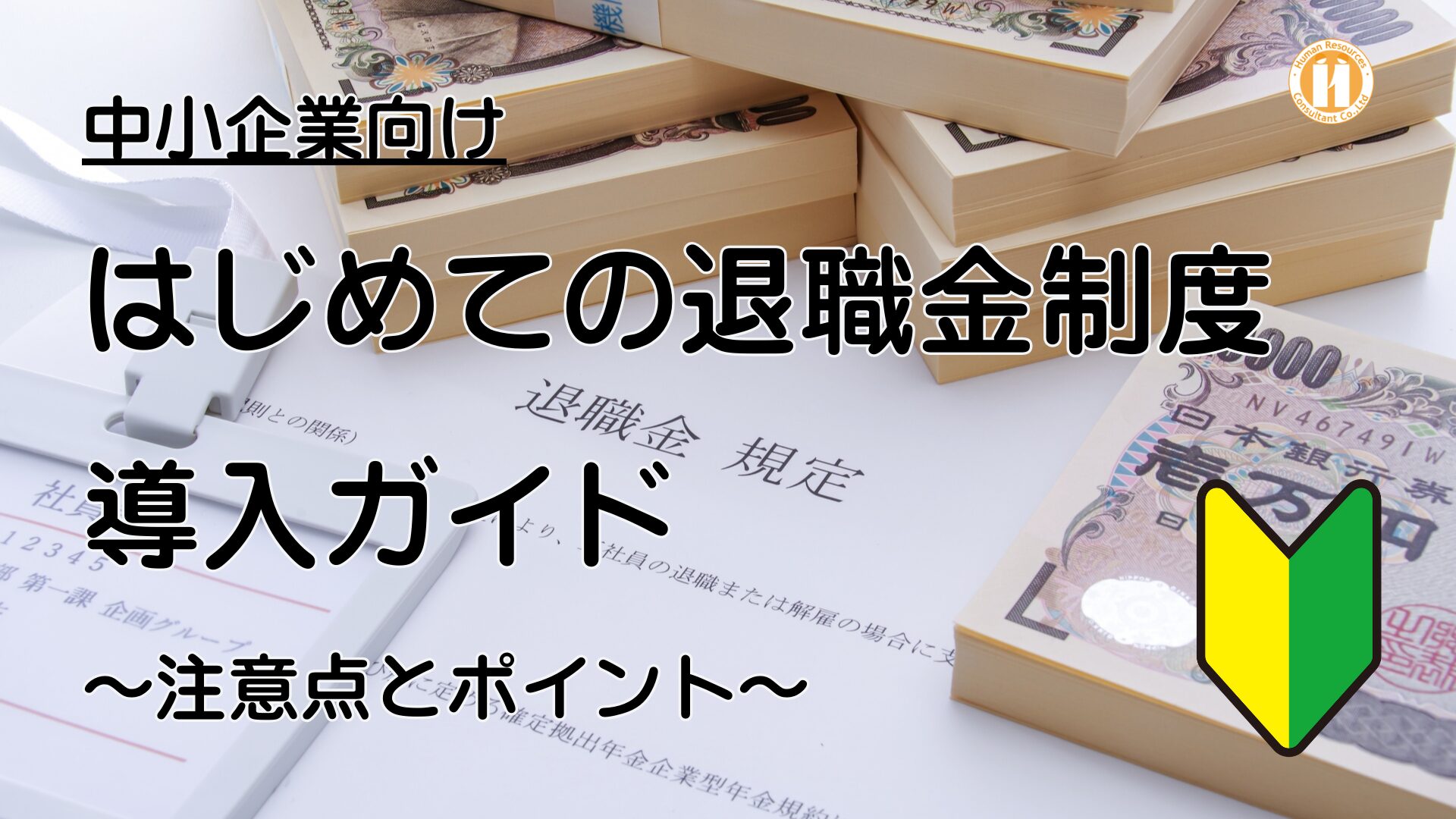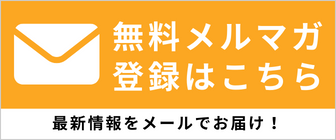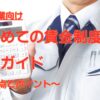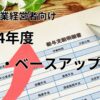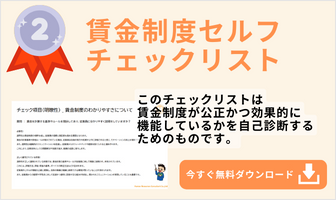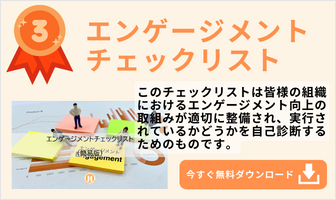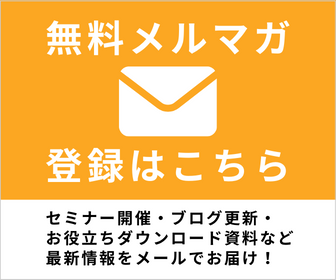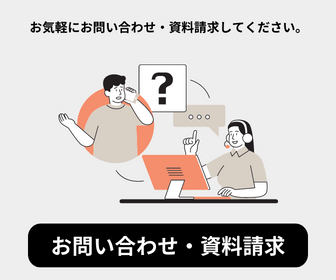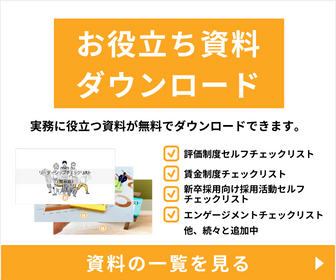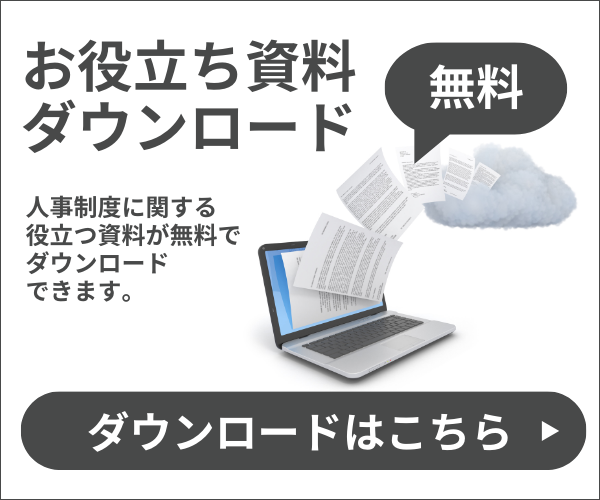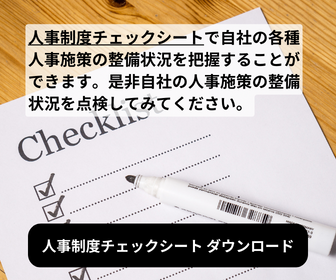中小企業向け | はじめて賃金制度を導入するときの注意点とポイント
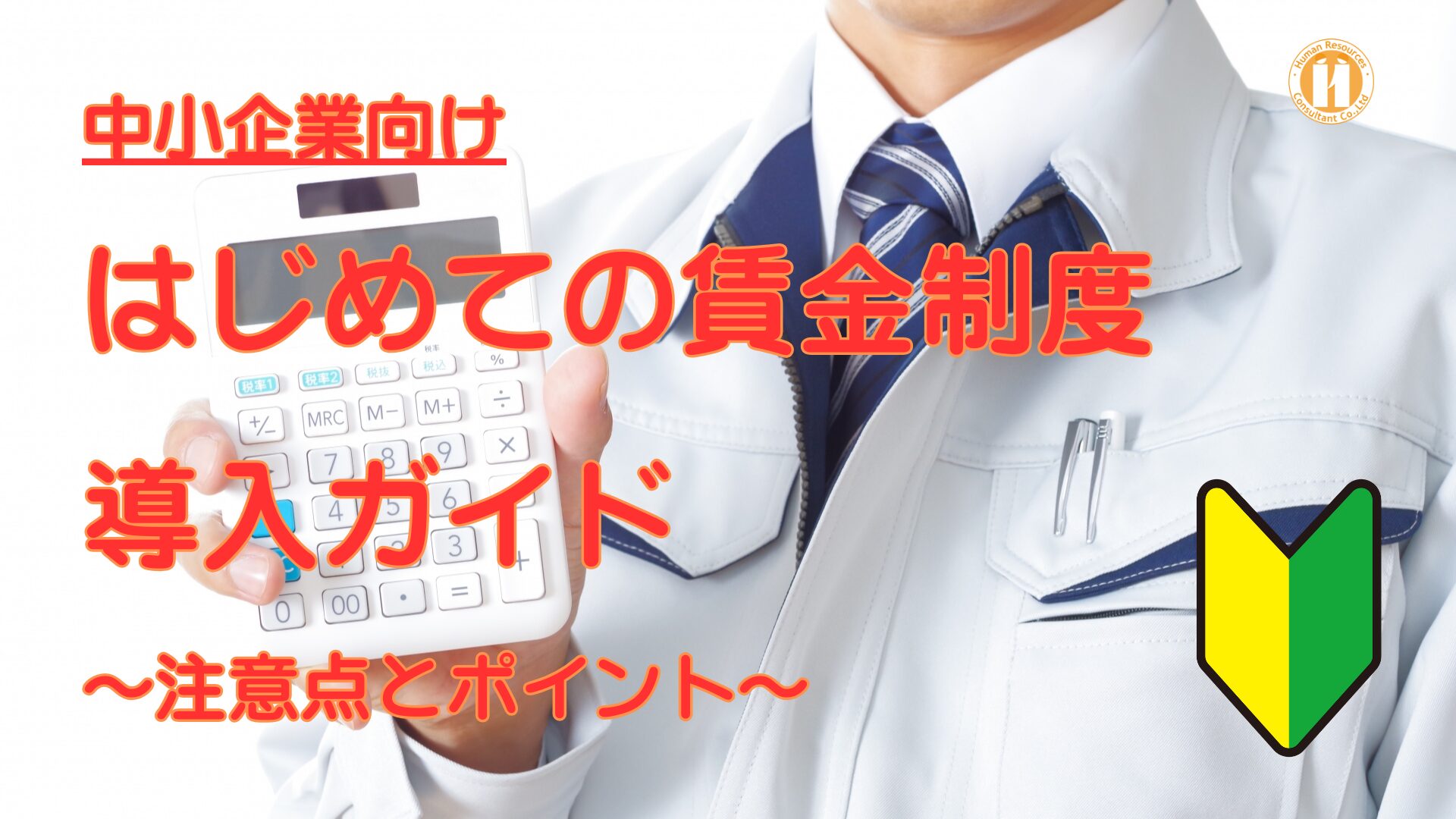
1. はじめに
本コラムでは、中小企業がはじめて「賃金制度」を導入する際に知っておきたい注意点やポイントについて、なるべく分かりやすい言葉で解説していきます。賃金制度というと、「大企業がやっている複雑な給与体系」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、企業規模を問わず、社員数が10名を超えた段階で「給与の決め方」や「昇給の基準」を明確にしないまま運営していると、社内に不満が生じたり、人材確保や人材定着に支障をきたすリスクが高まります。
そこで本コラムでは、まず賃金制度の必要性を感じる典型的なタイミングや場面についてお伝えします。そのうえで、戦後から現代にかけて日本でどのような賃金制度が運用されてきたのか、そのトレンド変遷をざっくりと押さえます。続いて、賃金制度を導入するメリットとデメリットを整理し、最後に「初めて賃金制度を導入するときの流れ」と「運用上の注意点」を詳しく解説していきます。
はじめて賃金制度に触れる経営者や人事担当者の方にも読みやすいよう、専門用語はなるべく丁寧に説明しながら進めていきます。最後まで読んでいただければ、賃金制度導入の全体像をイメージできるようになるはずです。それでは早速、賃金制度の必要性を感じる場面から見ていきましょう。
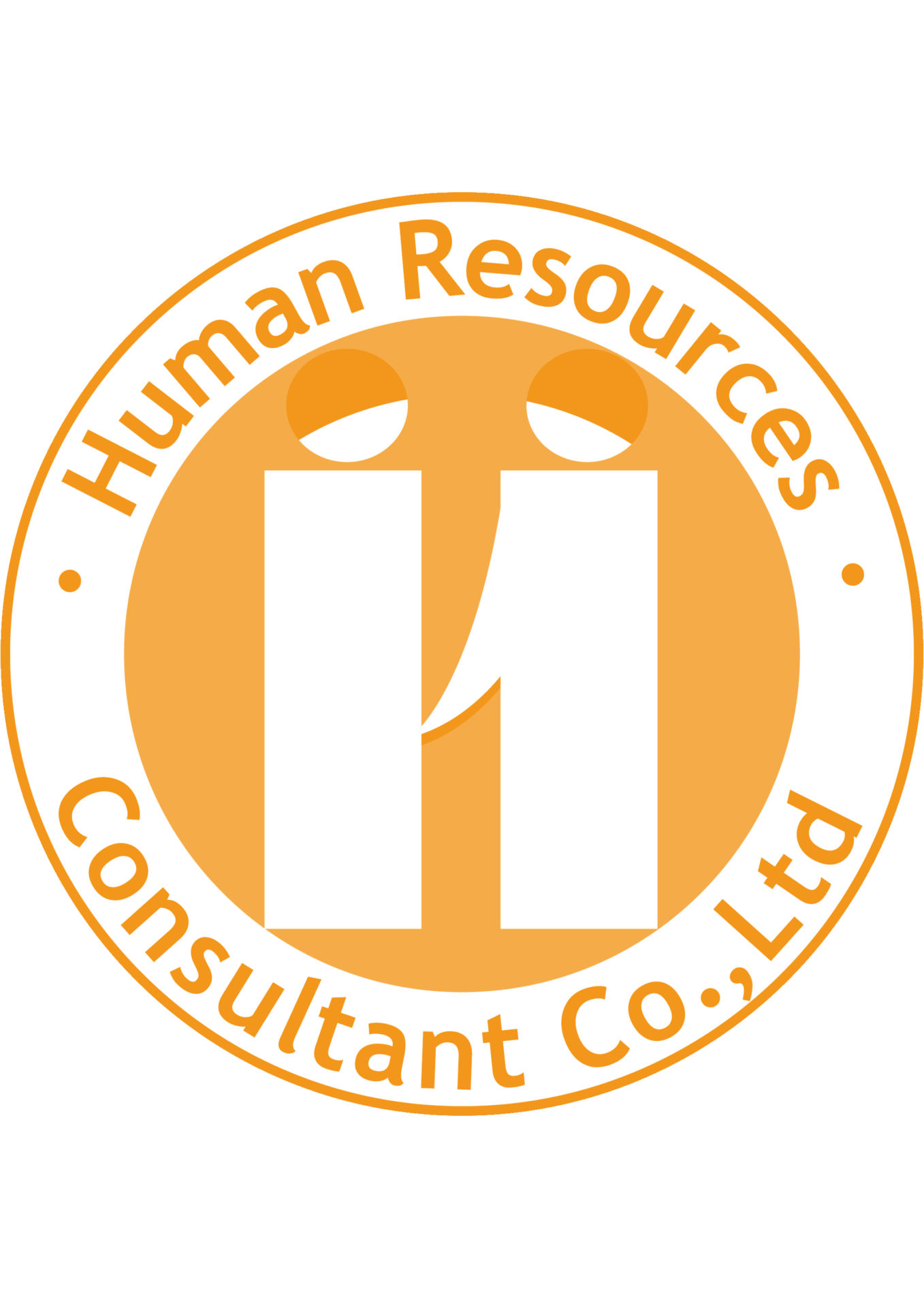
2. 経営者が賃金制度の必要性を感じるタイミングや場面
中小企業が「そろそろ賃金制度を導入したい」と考える背景には、さまざまな理由やタイミングがあります。ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
2-1. 社員数が増え、給与決定の根拠があいまいになったとき
創業当初は社長や役員が個別に面談し、業務の出来・不出来などを総合的に判断して給与を決めていたかもしれません。しかし、社員数が10名を超え、さらに増えていく中で「どのような基準で昇給やベースアップが行われているのか」があいまいになると、社員間で不公平感が生まれやすくなります。
「同じ時期に入社したAさんとBさんで、なぜこれだけ給与に差が出るのか」「どこまで成果を出せば昇給できるのか」などが不透明だと、モチベーションが低下する社員も出てきます。こうした声を受けて、「客観的な評価や賃金テーブルを作らなければ」という必要性を感じる経営者は少なくありません。
2-2. 人材確保や人材定着に課題を感じ始めたとき
中小企業が優秀な人材を採用するには、「給与条件の魅力」も無視できない要素です。もちろん企業文化や経営者の魅力、仕事のやりがいも重要ですが、求職者が複数社を比較検討するときには「将来の昇給の仕組みが整っているか」「キャリアアップに応じた賃金テーブルがあるか」といった点も大きな決め手になります。
すでに在籍している社員についても「評価や昇給が曖昧なままでは将来が見えない」と感じて退職を検討するケースが増えることがあります。せっかく教育・育成してきた人材が流出する前に、きちんとした賃金制度を整備することで人材定着率を上げたい、と考える経営者も多いです。
2-3. 組織経営への転換を図りたいとき
家族的経営から本格的な組織経営へ移行する段階では、経営者の「感覚」で給与を決めるのではなく、客観的・合理的な仕組みが求められるようになります。特に新規事業の立ち上げや部門拡大など、組織形態の変化が進む中で、社員が納得しやすい賃金テーブルや昇給基準を整備することは、社内のモラルや信頼感を保つうえでも重要です。
2-4. 役職・能力に応じた給与体系が必要になったとき
社員が増えてくると、役職の階層や業務の専門性に応じて給与を変動させる必要が出てきます。例えば、主任・課長・部長といった役職ごとに責任の範囲が異なり、求められるスキルやリーダーシップも変わるため、それを反映した賃金体系を設けないと不公平感が生まれがちです。「役割給」「職能給」「コンピテンシー評価」など、さまざまな導入事例があるので、自社の規模や業種・業態に合った仕組みを検討することが大切です。
3. 戦後の日本における賃金制度のトレンド変遷
賃金制度は時代の流れとともに変化してきました。戦後から現在に至る日本の賃金制度の主なトレンド変遷を理解しておくと、自社にどのような制度が合いそうか、ある程度のヒントを得ることができます。
3-1. 戦後から高度経済成長期:年功序列・終身雇用が中心
第二次世界大戦直後から高度経済成長期にかけては、多くの企業で「年功序列」と「終身雇用」を前提とする賃金体系が主流でした。
- 年功序列:勤続年数や年齢が上がるごとに自動的に給与も上がる仕組み
- 終身雇用:定年まで1つの会社で働くことを前提とする制度
この時代は経済が右肩上がりで、人手不足も相まって企業と社員の関係が「長期雇用を保障し、社員は忠誠を尽くす」という形で成り立っていました。そのため、給与も勤続年数に比例して上がっていくのが当然という考え方が広く浸透していました。
3-2. バブル期以降:能力主義や成果主義の台頭
高度経済成長が落ち着き、バブルが崩壊した後の時代には、年功序列・終身雇用の制度に限界が見え始めました。そこで、多くの企業が「能力主義」「成果主義」を取り入れ、社員一人ひとりのスキルや業績に応じた賃金制度を整備する動きが加速しました。
- 能力主義:専門知識や資格、実務経験などの“能力”を評価して給与に反映
- 成果主義:売上や利益などの“成果”に応じて給与や賞与を決定
この時代には「目標管理制度(MBO)」や「年俸制」といったキーワードも流行し、成果を明確に数値化することで評価する仕組みが注目されました。ただし、過度な成果主義によって社内競争が激化したり、短期的な数字ばかりを追いかける風潮が強まるというデメリットも浮上してきました。
3-3. 現在:多様化する働き方・価値観に合わせた柔軟な賃金制度
現代ではIT化・グローバル化の進展に伴い、働き方や社員の価値観が多様化しています。リモートワークやフレックス制、職務限定正社員、パートタイム正社員など、従来のフルタイム常勤だけに限定されない雇用形態が増えているのが特徴です。
そのため、企業には「職務内容に応じて給与を決定するジョブ型賃金制度」や「能力・スキルの発揮度合いを評価するコンピテンシー型給与」など、柔軟な制度設計が求められています。特に中小企業でも、専門性の高い人材を確保するために、成果主義や市場価値に見合った報酬制度を導入するケースが増えてきました。
4. 賃金制度を導入するメリットとデメリット
ここからは、実際に賃金制度を導入した場合のメリットとデメリットを整理していきます。どんな制度にも一長一短があるため、導入前にしっかりと把握しておくことが重要です。
4-1. メリット

組織における給与の根拠が明確化し、社員の納得度が高まる
賃金テーブルや評価基準をきちんと定めると、「なぜ自分の給与がこの金額なのか」が社員にとって分かりやすくなります。結果として、モチベーション向上や仕事へのコミットメントが強まり、人間関係のトラブルや不満の軽減にもつながります。
社員のモチベーション向上や人材育成につながる
能力主義や成果主義など、明確な評価基準を設けることで、社員は具体的な目標を持って業務に取り組むようになります。また、評価プロセスの中でフィードバックが行われやすくなるため、人材育成やスキルアップにも役立ちます。
適正人件費の把握・管理がしやすくなる
給与額が担当業務や役職、スキルレベルなどとリンクされるようになると、経営側としても人件費を予算化しやすくなります。組織規模や事業計画に応じて、必要な人材をどのようなコストで確保すべきかが見えやすくなり、経営判断のスピードアップにつながります。
経営判断のスピードアップ
昇給や昇格、配置転換などの判断基準が整備されていると、経営者や人事担当者はスムーズに人事異動を行いやすくなります。特に中小企業では一人ひとりの働きが経営に大きく影響するため、迅速かつ適切な意思決定が求められます。賃金制度があると、こうした場面での迷いが減ります。
4-2. デメリット

導入・運用コストがかかる
賃金制度を設計し、運用ルールを定め、社員や管理職に周知徹底するためには時間とコストがかかります。制度の策定には専門知識が必要な場合も多く、コンサルタントや社労士への依頼費用などが発生することも考慮しておかなければなりません。
基準が固定化・形骸化し、柔軟な対応ができなくなるリスク
導入当初は意義を持って始めた制度でも、時代の変化や事業内容の拡大、社員構成の変化に対応できず、形だけが残るケースがあります。そうなると「この評価シートを埋めるためだけに頑張る」という本末転倒な状態に陥り、組織の創造性や柔軟性が損なわれる恐れがあります。
賃金格差や評価の不透明感が生じた場合、社内不満の原因となる
社員間の仕事内容や成果に大きな差がある場合、能力主義や成果主義を取り入れることで賃金格差が明らかになることがあります。それ自体は一定の合理性があるとしても、社員側が納得できる説明やフィードバックがなければ、不満が噴出する可能性があります。また、評価基準や評価者の目線がばらついている場合、制度そのものに対する不信感が高まるリスクがあります。
5. 初めて賃金制度を導入する流れと注意点
それでは、実際に賃金制度を導入する際には、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは代表的な導入の流れと、各ステップでの注意点をまとめます。
5-1. 導入の流れ
現状把握・課題分析
まずは自社の現状をしっかりと把握し、賃金に関する課題を洗い出します。経営者や管理職だけでなく、社員へのアンケートやヒアリングを通じて「昇給ルールが分からない」「仕事量と給与が見合っていない」といった声を集めるのも効果的です。ここで明確になった課題が、賃金制度設計の方向性を示す重要な材料となります。
賃金制度の目的・方針設定
次に、「なぜ賃金制度を導入するのか」「どんな組織を目指すのか」という目的や方針を明確にします。たとえば「能力開発を促進したい」「優秀な人材を引き留める仕組みにしたい」「業績向上のために成果を重視したい」など、企業ごとに異なる優先順位があるはずです。この段階で経営層がしっかりと腹をくくり、共通の認識を持っておくことが後々のブレを防ぎます。
賃金テーブル・評価基準の策定
次に、実際にどのような仕組みで賃金を決定するのかを具体的にデザインします。代表的な例としては以下があります。
- 等級制度(職能資格制度):社員を能力や職責に応じた等級に分類し、等級ごとに給与幅を設定する
- 職務給・役割給:職務や役割の重要度・責任範囲に応じて給与水準を決める
- コンピテンシー評価:成果だけでなく、行動特性や発揮されたスキルを重視する
中小企業の場合、一人が複数の役割を兼務することも多いので、あまりに細分化しすぎると運用が複雑になりがちです。シンプルで分かりやすいテーブルにまとめることがポイントです。
運用ルールの決定
「年に何回評価を行うか」「昇給のタイミングはいつか」「評価結果を賞与にどの程度反映させるか」など、具体的な運用ルールを決めます。評価者の選定(上司のみか、360度評価を取り入れるか)や評価会議の手順なども、ここで整理しておくと混乱が少なくなります。
社内説明・評価者研修
制度設計がまとまったら、社内に向けて賃金制度の全体像や狙いをしっかり周知しましょう。特に、社員にとっては「どのように評価されるのか」が大変気になるポイントです。評価シートの書き方や面談の進め方などについても具体的に説明することで、不安や誤解を減らせます。
また、評価者研修(管理職やリーダー向けの研修)を行い、適切な評価の進め方を学んでもらうことは必須です。評価基準が曖昧だと、どれだけ制度が整備されていても上手く機能しません。
試行運用・フィードバック
最初から全社で一斉導入するのではなく、まずは一部部署や特定の職種でテスト運用してみるのも有効です。試行運用中に「評価項目が多すぎて集計が大変」「評価者が忙しくて面談が形骸化している」などの問題点が見つかった場合、そこを改善してから全社的に導入したほうがスムーズにいきます。
本格導入・定期的な見直し
試行運用のフィードバックを踏まえたうえで、本格的に全社で賃金制度を導入します。導入後は一回きりで終わりではなく、経営環境の変化や組織の成長スピードに合わせて定期的に制度を見直すことが重要です。新しい事業を始めたり、外部人材を積極的に採用したりする際にも、賃金制度が現状と合っているかをチェックして柔軟にアップデートしていきましょう。
5-2. 注意点
経営層・管理職の理解と一貫性
経営者や管理職が賃金制度の目的や運用方法をしっかり理解していないと、現場レベルで戸惑いが生じたり、評価のばらつきが顕在化しやすくなります。トップマネジメントによる一貫したメッセージと実行が、社員の納得感を高める鍵です。
社員とのコミュニケーションを大切に
給与や評価は社員の生活やキャリアに直結します。制度の導入時や運用ルールの変更時には、なぜその判断に至ったのか、どういったメリットやデメリットがあるのか、丁寧に説明することが大切です。ここをおろそかにすると、不信感や反発を招きやすくなります。
制度が目的化しないようにする
賃金制度はあくまでも組織目標を達成するための手段であり、導入そのものがゴールではありません。運用が始まると「評価シートを埋めること」が目的になったり、「昇給のための点数稼ぎ」だけに注力する社員が出てくる可能性があります。制度と経営戦略との連動を意識し、成果創出や能力開発に結びつける運用を心がけましょう。
変化に対応するための定期的な見直し
会社の事業ステージや市場環境、人材構成は年々変化します。導入時には自社に合っていた制度も、3年後・5年後には合わなくなっていることが珍しくありません。定期的に制度を検証し、必要に応じて改訂や追加を行うことで、常に自社にフィットした仕組みを維持できます。
6. まとめ
ここまで「中小企業向け|はじめて賃金制度を導入するときの注意点とポイント」と題して、賃金制度の必要性や日本における戦後から現代までのトレンド変遷、導入のメリット・デメリット、そして具体的な導入の流れと注意点をご紹介してきました。賃金制度は、社員数が10名を超えたあたりから検討を始める企業が多いですが、これは単に「どのように給与を決めるか」というだけでなく、「どのように人材を育成し、組織を成長させるか」という経営課題とも深く結びついています。
戦後の日本では年功序列・終身雇用が当たり前の時代を経て、バブル崩壊以降は能力主義・成果主義が広がりました。そして現代では働き方の多様化に合わせて、コンピテンシーやジョブ型など、より柔軟な賃金制度が注目されています。中小企業でも、事業環境に合わせて賃金テーブルを設計し、社員の納得感と会社の成長を両立させることが大切です。
メリットとしては、組織全体のモチベーションアップや人材定着、人件費管理の明確化などが期待できます。一方で、導入コストや運用の手間、不適切な評価が生む社内不満などのデメリットやリスクも存在します。これらを理解したうえで、正しい手順を踏み、経営層から徹底したコミットメントを行うことで、賃金制度は会社の大きな武器となり得るでしょう。
導入ステップとしては、まず現状把握と課題分析を行い、賃金制度の目的・方針を明確にします。そのうえで賃金テーブルや評価基準を設計し、運用ルールを定めたら社内説明・評価者研修を実施します。可能であれば試行運用を経てから本格導入し、定期的に見直す流れが一般的です。
最後に、賃金制度をつくる際に重要なのは「制度が目的化しないようにすること」です。企業が成長するうえで、社員がどのように働き、どんな成果や行動を期待されているのかをはっきり示す手段として賃金制度がある、という意識を忘れないでください。制度を適切に運用し、経営戦略と連動させることで、中小企業でも大企業に負けない組織力を発揮できるはずです。
投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。