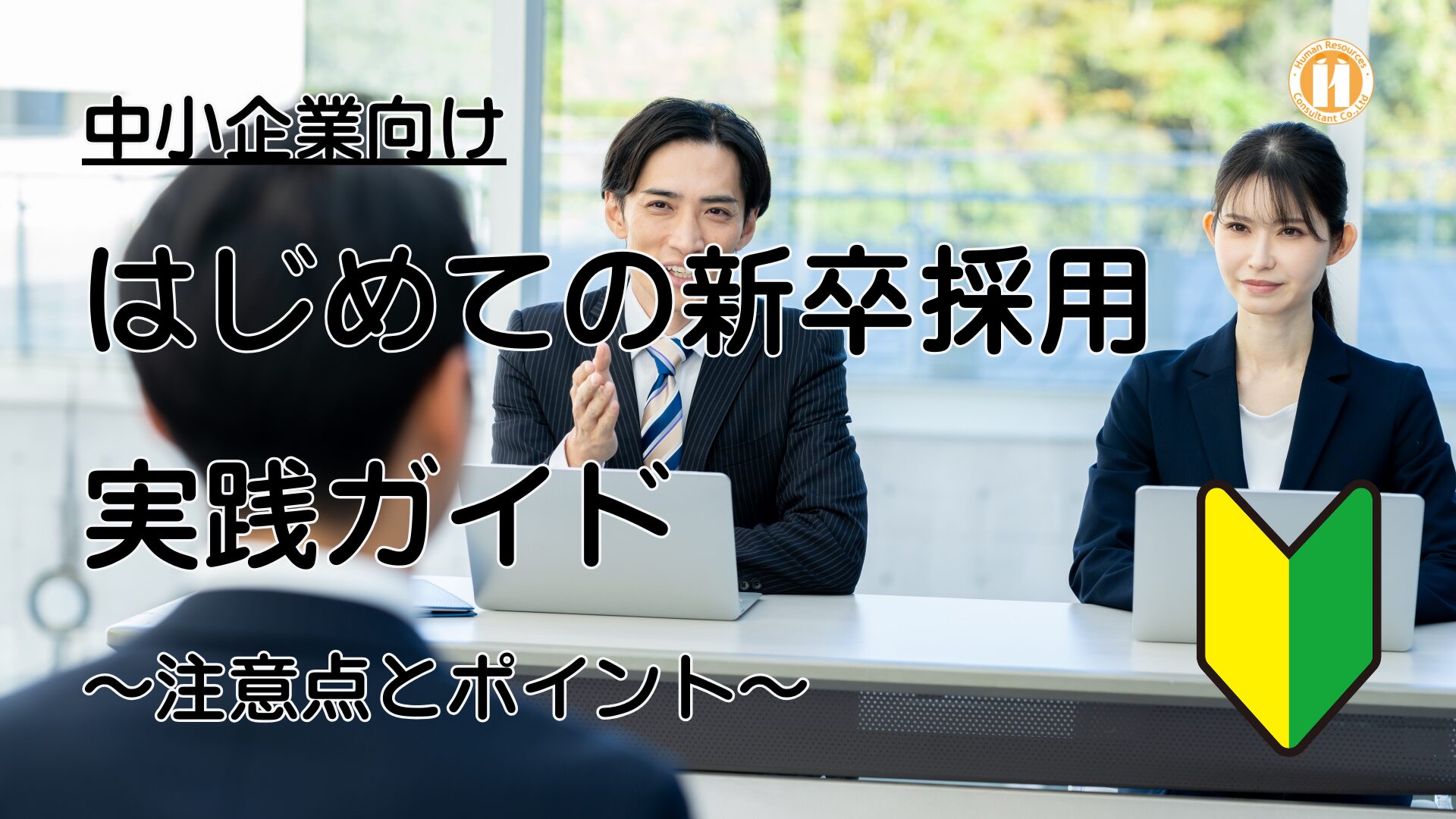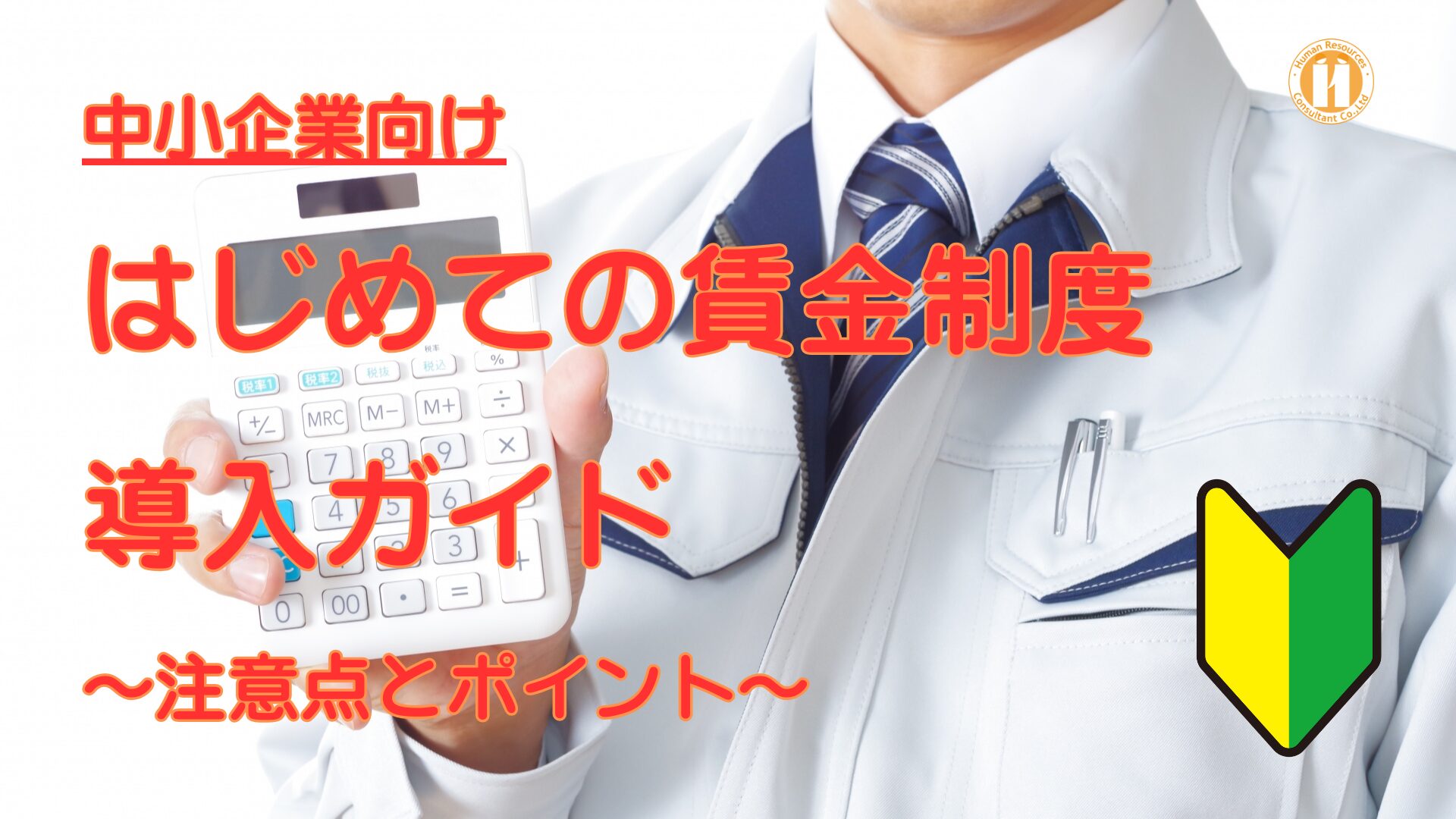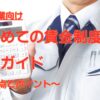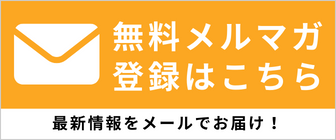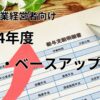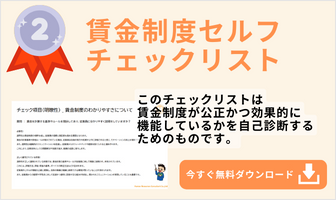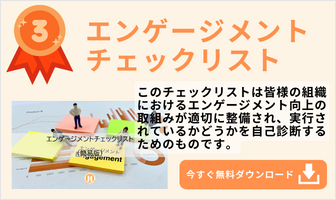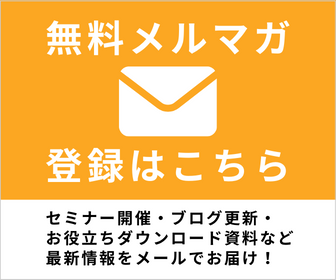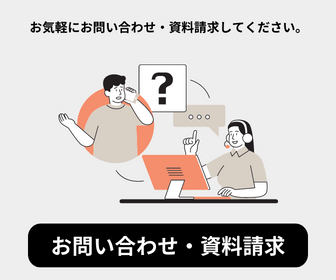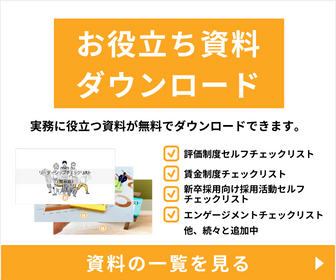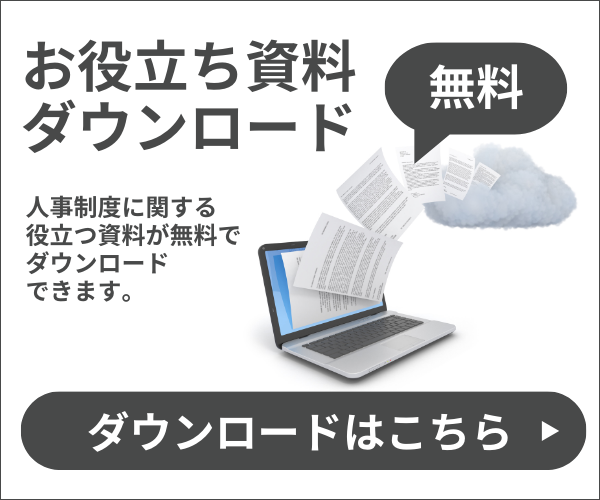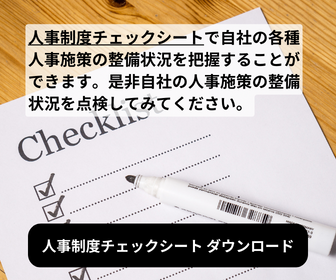中小企業向け | はじめて退職金制度を導入するときの注意点とポイント
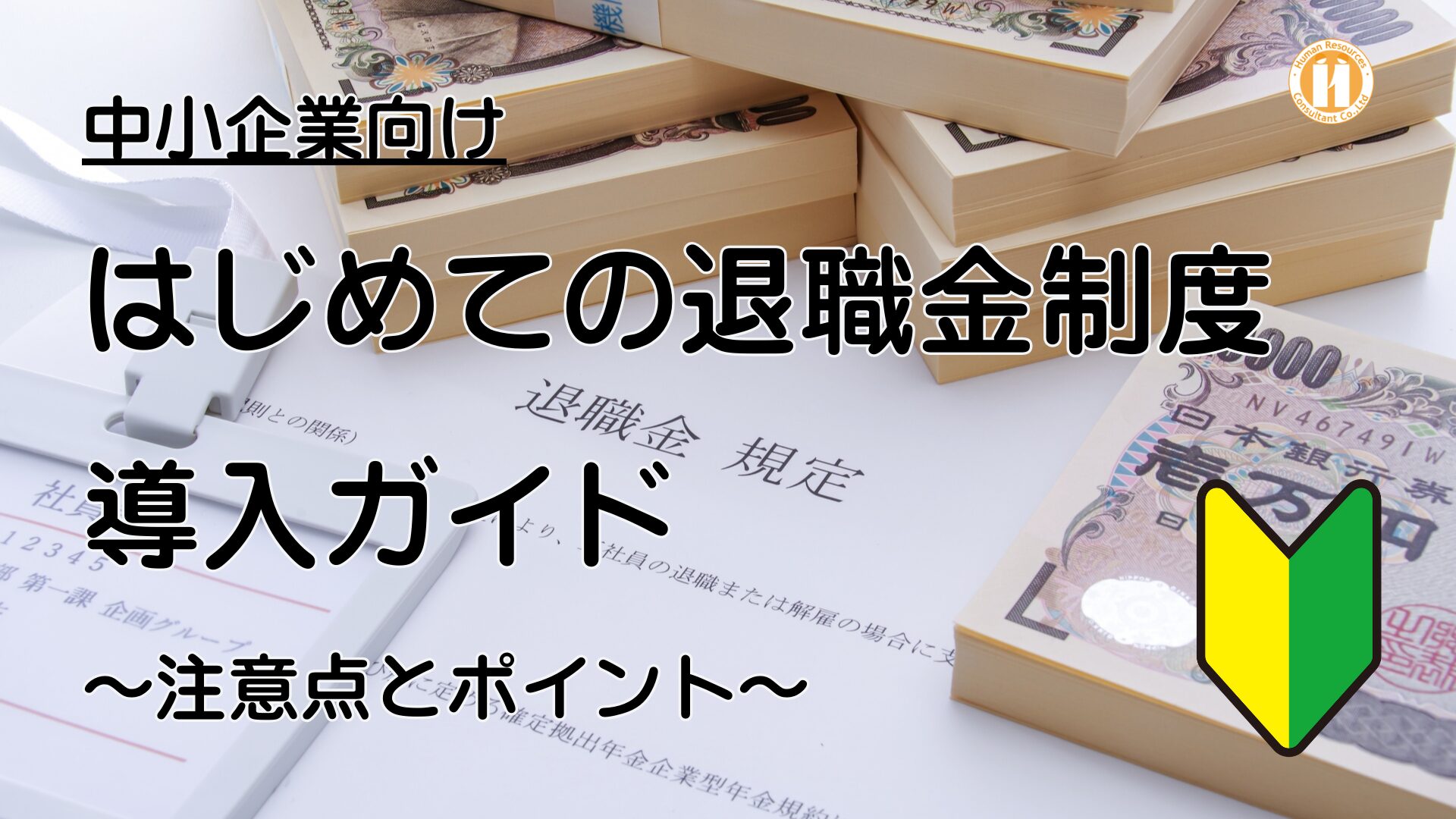
1. はじめに
本コラムでは、中小企業がはじめて「退職金制度」を導入するときに押さえておきたい注意点やポイントを分かりやすく解説します。退職金制度というと、大企業だけが取り入れるようなイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、社員数が10名を超えた段階で、福利厚生の一環や人材定着の施策として退職金制度を検討する中小企業は年々増えています。
退職金制度は、企業にとっては長期的な財務負担が伴う仕組みである一方、社員にとっては「老後資金」や「キャリアの区切り」のための大切な報酬ともいえます。制度を導入することで、「社員の勤続意欲が高まる」「採用時に他社より優位に立てる」といったメリットも期待できますが、同時に「運用コストが増える」「社員に誤解を与えるリスクがある」などのデメリットも存在します。
本コラムでは、まず経営者が退職金制度の必要性を感じるタイミングについて整理します。次に、戦後から現在までの日本における退職金制度のトレンド変遷をざっくりと押さえます。そのうえで、導入メリット・デメリットを解説し、最後に「初めて退職金制度を導入する流れ」と「運用上の注意点」をご紹介します。
文章はすべて「ですます調」で統一し、退職金制度に詳しくない方でもイメージしやすいように構成しております。ぜひ参考にしていただき、退職金制度導入の検討を具体的に進めるきっかけにしていただければ幸いです。
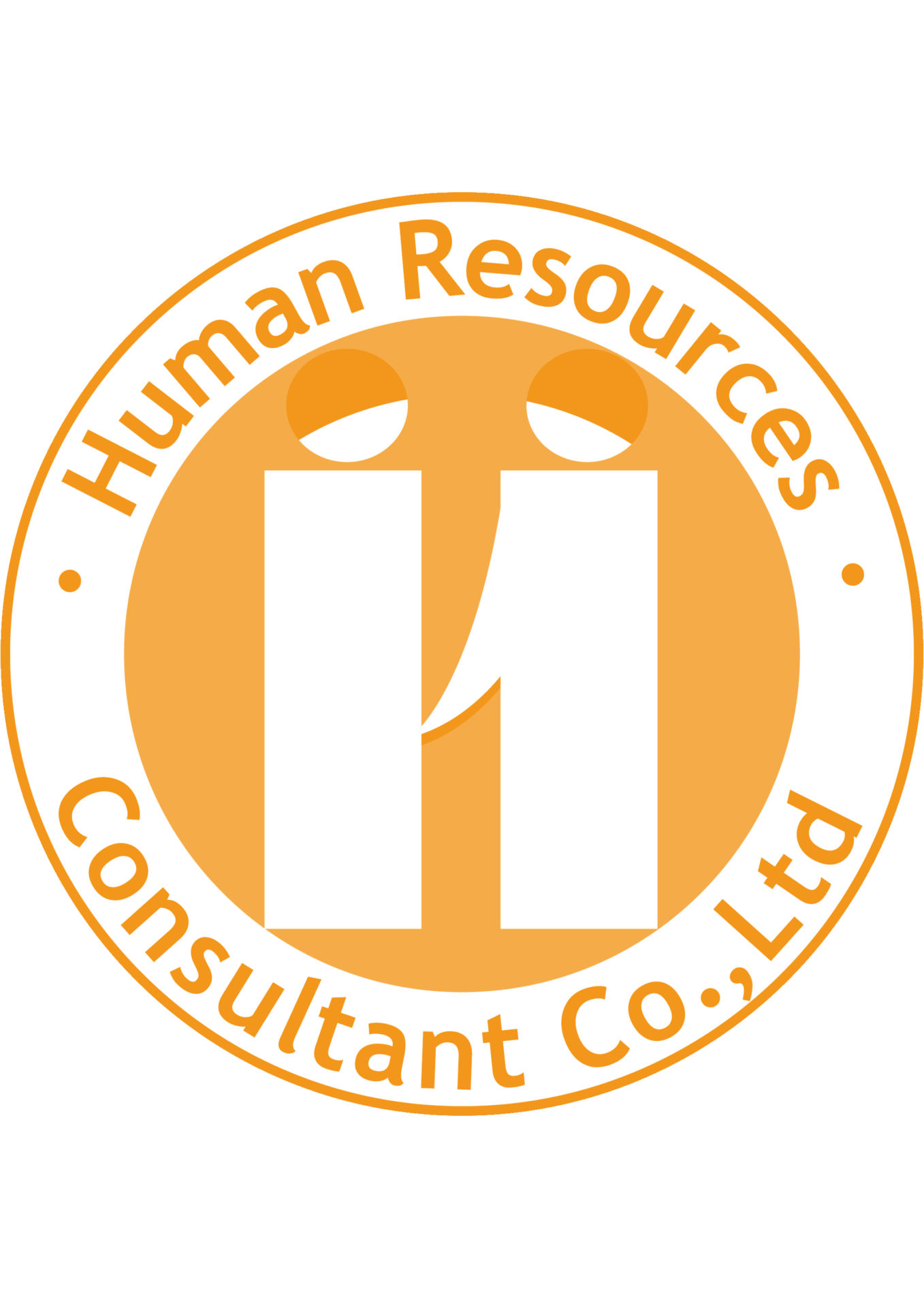
2. 経営者が退職金制度の必要性を感じるタイミングや場面
まずは、中小企業の経営者が「退職金制度を整備しなければ」と考える代表的なタイミングや場面を見ていきましょう。
2-1. 社員の勤続年数が長くなり、将来設計に対するニーズが高まったとき
中小企業の創業初期は社員の入れ替わりも激しく、退職金制度を設ける余裕がなかったかもしれません。しかし、5年、10年と勤続する社員が増え始めると、社員側から「老後資金をどう考えればいいのか」「退職時にまとまったお金が欲しい」といった声が出てくることがあります。こうしたニーズを受けて、企業としても退職金制度を整える必要性を感じるケースが多いです。
2-2. 人材確保・人材定着の施策として福利厚生を充実させたいとき
近年は「働き方改革」や「人生100年時代」という言葉が広がり、社員が長く安心して働ける環境を整えることが企業の重要なミッションとなっています。退職金制度の有無は、求人募集の際に応募者が企業を選ぶ大きな基準のひとつにもなり得ます。特に同業他社が既に退職金制度を取り入れている場合は、自社も整備しておかないと採用競争で不利になるかもしれません。
2-3. 大企業や他社との比較で、退職金制度の未整備が気になり始めたとき
中小企業でも優秀な人材を採用しようとすると、大企業や外資系企業の待遇と比較される場面は少なくありません。賞与や給与体系だけではなく、退職金制度の有無も「将来の安心感」を左右する重要な要素です。優秀な人材を確保するうえで「退職金制度がない企業」というイメージを持たれるのは大きなデメリットとなる場合があります。
2-4. オーナー経営から組織経営へ移行したいとき
家族経営から本格的な組織経営へと転換を図る際に、給与や賞与とは別の長期的報酬制度を整える必要性を感じる経営者も少なくありません。退職金制度があることで、社員は「この会社で長く働けば、それに見合う報酬がきちんと用意されている」と安心し、モチベーションが高まります。事業拡大に伴い社員数や職種が増えてくると、退職金制度を含めた人事制度全体の整備が必要になるのは自然な流れです。
3. 戦後の日本における退職金制度のトレンド変遷
退職金制度は日本の労働文化と密接に結びついて発展してきました。ここでは、戦後から現在に至るまでの大まかな変遷を押さえ、背景となる社会環境や企業の動きを簡単に確認しましょう。
3-1. 戦後〜高度経済成長期:勤続のご褒美としての退職金
第二次世界大戦後から高度経済成長期にかけて、日本の企業社会は「年功序列」と「終身雇用」を軸に発展してきました。長期雇用を前提としていたため、退職金は「長年勤め上げてくれた社員へのご褒美」「給与の後払い」と位置づけられていました。
当時は社員が定年まで勤めるのが当たり前だったことから、退職金制度を備える企業は多く、退職金も「勤続年数×一定の係数」で算出されるような仕組みが一般的でした。
3-2. バブル期以降:企業年金や確定給付型制度の見直し
バブル経済が崩壊した1990年代以降、日本企業の経営環境は大きく変化し、業績が悪化する中で従来の確定給付型退職金制度(DB:Defined Benefit)が重い財務負担となるケースが増えました。企業年金を含め、退職金にかかるコストが経営を圧迫した結果、退職金制度の見直しを行う企業が相次いだのです。
この頃から、アメリカ式の「401kプラン」をベースにした**確定拠出年金(DC:Defined Contribution)**が注目され始めました。企業が拠出金を一定額負担し、社員がその資金を運用して老後資金を形成する仕組みです。企業側は将来の年金支払いリスクを抑えられるというメリットがあり、社員側も自己責任で資産運用を行うため、多様な投資商品を選べるようになりました。
3-3. 現在:多様な働き方・雇用形態に合わせた柔軟な退職金制度
IT化やグローバル化の進展に伴い、働き方が多様化する中で退職金制度にも様々なオプションが生まれています。代表的なものとしては、以下が挙げられます。
- 中小企業退職金共済(中退共):中小企業が手軽に退職金を準備できる共済制度。掛金は経営状況に合わせて見直し可能。
- 確定給付企業年金(DB):企業が将来の給付を保証する方式。ただし、財務リスクが大きいため導入には注意が必要。
- 確定拠出年金(DC):企業が拠出金を一定額負担し、社員自身が資産運用を行う方式。401kとも呼ばれることがある。
- 企業型保険商品:企業独自の保険契約を用いて退職金を積み立てる方法。
中小企業の場合は「中退共」や「確定拠出年金(DC)」など、比較的導入しやすい制度を活用するケースが増えてきています。いずれにしても、社員の人生設計や企業の財務戦略に合わせて、最適な仕組みを選ぶことが重要です。
4. 退職金制度を導入するメリットとデメリット
ここでは、退職金制度を導入することで得られるメリットと、注意すべきデメリットを整理します。どの制度にも一長一短があるため、企業の状況や方針を踏まえて検討することが大切です。
4-1. メリット

従業員の将来設計をサポートし、人材定着や社員満足度の向上につながる
退職金制度があることで、社員は「長く働けば、それに見合う報酬が用意されている」という安心感を得られます。特に、老後資金やセカンドキャリアの準備に不安を抱える社員にとって、退職金制度は大きな魅力となります。結果として、人材の定着率が高まり、社員満足度を向上させる効果が期待できます。
採用活動において福利厚生が充実している企業としてアピールできる
退職金制度が整備されていることは、応募者に対して「社員を大切にする企業」という印象を与えやすくなります。特に中途採用で複数社を比較検討している応募者の場合、退職金制度の有無が就職先を選ぶ決め手になることもあります。
長期的なインセンティブを設けることで社員のモチベーションが高まる
退職金制度があることで、社員の意識は短期的な給与や賞与だけでなく、将来的な報酬にも向かうようになります。これは企業側から見れば、「長く働いて成果を出し続ければ、最後に報われる」というメッセージにもなり、社員のモチベーションや会社へのロイヤルティを育む効果が期待できます。
4-2. デメリット

制度設計や運用にかかるコストが発生する
退職金制度を導入する際は、具体的なルールや規程を作成し、就業規則にも反映させる必要があります。確定給付型を導入する場合は、将来の給付原資をどのように積み立て、運用するかを考えなければならず、専門的な知識や財務上の備えも必要になります。導入時の初期コストや、制度を維持していくためのランニングコストが経営を圧迫する可能性もあります。
財務リスクが増える可能性がある
確定給付型(DB)の退職金制度の場合、将来の給付額があらかじめ約束されているため、企業が業績不振や景気変動に直面したときでも、退職金を支払う義務が生じます。その結果、積立不足に陥るリスクが高まり、企業のキャッシュフローを圧迫する原因となることがあります。
また、運用商品次第では退職金資産が目減りする可能性があり、リスクマネジメントが難しい点にも注意が必要です。
社員に誤解や不公平感を与えるリスク
退職金制度の内容や計算方法が複雑だったり、説明が十分でなかったりすると、社員が「自分がどれだけ受け取れるか」を正しく理解できず、不公平感や不信感を抱く可能性があります。特に、退職金の支給要件が勤続年数によって大きく左右される場合、短期勤務の社員が不満を持つケースも考えられます。
5. 初めて退職金制度を導入する流れと注意点
具体的に退職金制度を導入するにはどのような手順を踏めばいいのでしょうか。ここでは、代表的な導入ステップと、それぞれの段階での注意点を解説します。
5-1. 導入の流れ
現状把握・目的の明確化
まずは自社の財務状況と人件費構造を把握し、退職金制度をなぜ導入するのかを明確にします。具体的には、以下のような点をチェックするとよいでしょう。
- 人材確保・人材定着を強化したい
- 社員の老後資金形成をサポートしたい
- 大企業や同業他社と比較して魅力を高めたい
ここで「退職金制度で解決したい課題」をはっきりさせておくと、後々の制度設計がスムーズになります。
制度タイプの検討
退職金制度には大きく分けて確定給付型(DB)と確定拠出型(DC)、そして中小企業退職金共済(中退共)などの仕組みがあります。自社の規模や資金繰り、社員の構成や将来の見通しを踏まえて、最適な方法を選びましょう。
- 確定給付型(DB):将来の給付額があらかじめ確定している。企業側に財務リスクが大きい。
- 確定拠出型(DC):企業が一定額を拠出し、社員が運用して老後資金を形成。企業リスクは抑えられるが、社員側の運用リテラシーが求められる。
- 中退共:中小企業専用の退職金共済制度。社会保険労務士や金融機関も導入サポートを行っている。掛金は経営状況に応じて増減可能。
詳細設計・規程整備
どの制度タイプを導入するにしても、退職金規程や就業規則などを整備し、「退職金の支給条件」「算定方法」「受給手続き」などを具体的に定める必要があります。
- 勤続年数や役職、退職理由(定年・自己都合・会社都合など)に応じた計算式
- 退職金の支給タイミングや手続き
- 中途退職者への取り扱いルール(勤続3年未満の社員には支給しないなど)
ここで曖昧さが残ると、後々トラブルに発展することもあるため、なるべく明確なルール作りを心がけましょう。
専門家への相談
退職金制度は、税制や社会保険の仕組みとも密接に関連します。導入時には社内だけで判断せず、社会保険労務士や人事コンサルタント、金融機関などの専門家にアドバイスを求めると安心です。特に中退共や確定拠出年金(DC)を導入する際には、制度のメリット・デメリットをしっかり理解したうえで準備を進めましょう。
社内説明・周知
制度を設計したら、経営者や管理職はもちろん、全社員に向けて退職金制度の内容やルールをしっかり周知します。どのようなタイミングで、いくら支給される可能性があるのか、そして拠出金や運用の仕組みはどうなっているのかといったポイントを丁寧に説明しましょう。この段階で不明点や不満があれば率直に拾い上げ、制度導入前に解消しておくことが大切です。
試行・フィードバック
可能であれば、一部の部署や特定の役職で先行して導入し、実際の運用上の問題点を洗い出します。社員へのアンケートや面談を通じて「運用手続きが煩雑」「説明が分かりづらい」「拠出金額に対する不満がある」といったフィードバックを集め、適切な対応策を検討することが重要です。
本格導入・定期的な見直し
試行の結果を踏まえ、必要な修正を加えたうえで全社的に導入を進めます。導入後も、経営環境や社員構成の変化に合わせて制度が合わなくなる可能性がありますので、定期的に見直しを行いましょう。特に、法改正や税制改正があった場合は、その影響を受けて退職金規程をアップデートする必要が生じるかもしれません。
5-2. 注意点
財務負担の見込みを把握する
確定給付型の場合は将来の支給額をしっかり見積もり、計画的に積み立てや運用を行わないと、急な退職が重なったときに対応できなくなるリスクがあります。確定拠出型や中退共であっても、掛金の設定や社員の加入状況を定期的にモニタリングし、無理のない範囲で拠出する必要があります。
社員への説明・コミュニケーションを重視する
退職金制度は社員の長期的なライフプランに大きく関わるため、誤解や不安を与えると信頼を損ねかねません。社員にとって分かりやすい資料を用意し、具体的なシミュレーションを示すなど、コミュニケーションを丁寧に行うことが大切です。
経営戦略との連動を意識する
退職金制度は単なる「福利厚生」ではなく、企業の人材戦略とも密接にリンクしています。例えば、確定給付型を導入することで社員の長期定着を促すのか、確定拠出型を導入して若手社員に資産運用の意識を高めてもらうのか、といった方向性によって、組織の文化や人材活用の方針に影響が出ます。導入時には、経営者や人事部門が制度の目的をしっかり共有することが欠かせません。
法改正・社会情勢の変化への対応
日本の年金制度や税制は、社会情勢の変化や少子高齢化を背景に随時見直しが行われています。そのため、せっかく導入した退職金制度が数年後には法律の改定などで合わなくなる可能性もあります。定期的に情報をキャッチアップし、必要に応じて制度をアップデートするフットワークの軽さを持ちましょう。
6. まとめ
本コラムでは、中小企業がはじめて退職金制度を導入する際に知っておきたい注意点とポイントを、以下の流れで解説してきました。
- はじめに:退職金制度の導入背景や重要性
- 退職金制度の必要性を感じる場面:人材定着や採用競争力の向上など、中小企業が制度導入を検討するきっかけ
- 戦後の日本におけるトレンド変遷:年功序列・終身雇用の時代から、バブル崩壊後の確定拠出年金普及まで
- 導入のメリットとデメリット:社員満足度向上や財務リスクなど、両面を理解することの大切さ
- 導入の流れと注意点:制度タイプの検討から詳細設計、社内周知、試行運用、本格導入までのプロセス
退職金制度は、中小企業にとって決して小さくない投資です。しかし、人材確保・人材定着に効果を発揮し、社員のモチベーションや会社へのロイヤルティを高める大きな要素でもあります。実際に導入を進める際には、確定給付型(DB)や確定拠出型(DC)、中小企業退職金共済(中退共)といったさまざまな制度の特徴をしっかりと把握し、自社の経営方針や社員のニーズに合った仕組みを選ぶことが成功の鍵となります。
また、導入後も定期的な見直しや社員への説明・コミュニケーションを欠かさないことが重要です。社会保険労務士や人事コンサルタント、金融機関の専門家を上手に活用して、制度設計から運用、トラブルシューティングまでをトータルにサポートしてもらうと安心です。
最後に、退職金制度は「企業が社員を大切にし、長く働いてほしい」というメッセージを形にしたものでもあります。福利厚生が手薄になりがちな中小企業こそ、退職金制度の導入を真剣に検討することで、社員にとっても魅力的な職場環境を整えることができるでしょう。本コラムをきっかけに、ぜひ前向きな導入検討を進めてみてください。
投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。