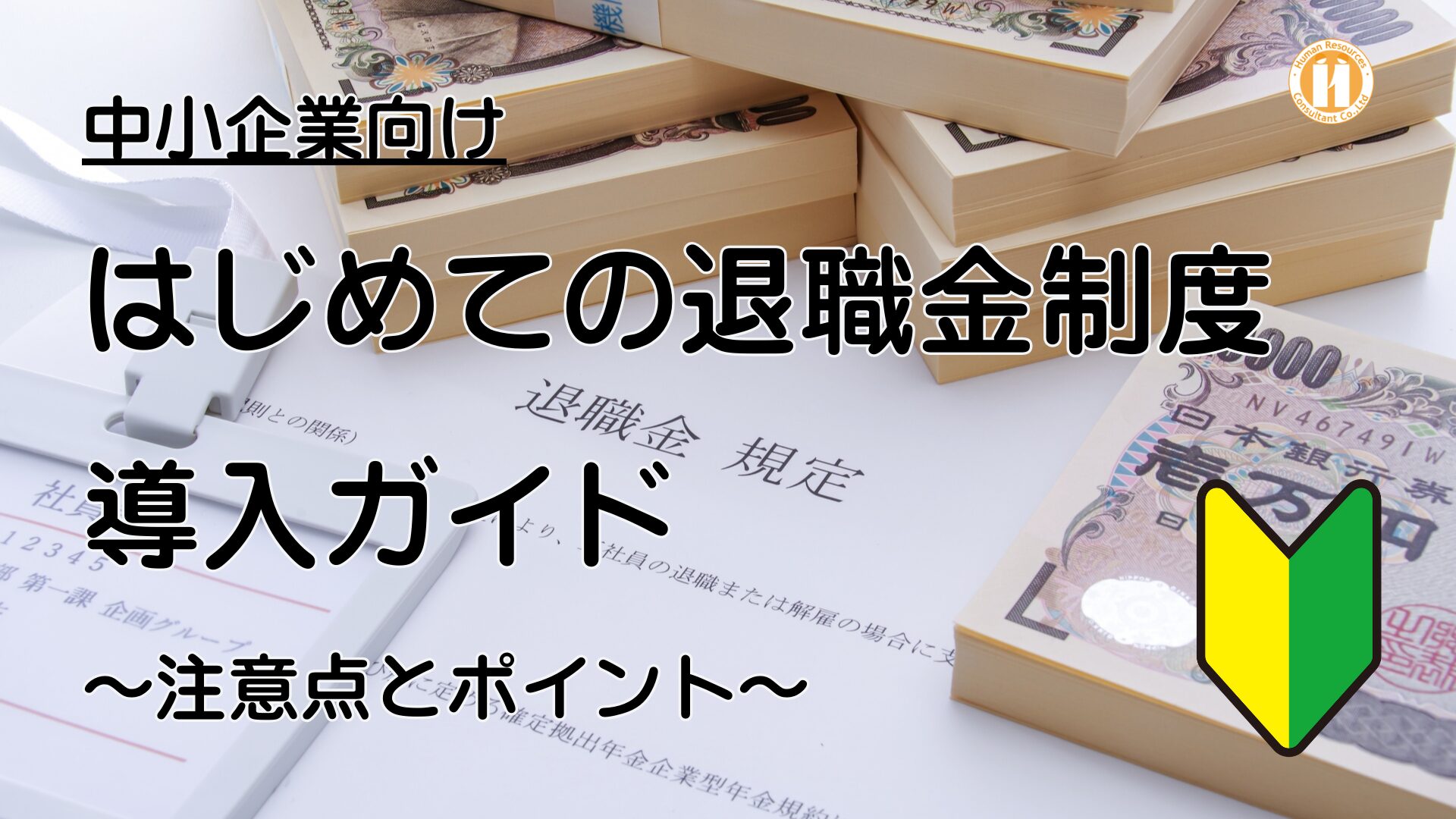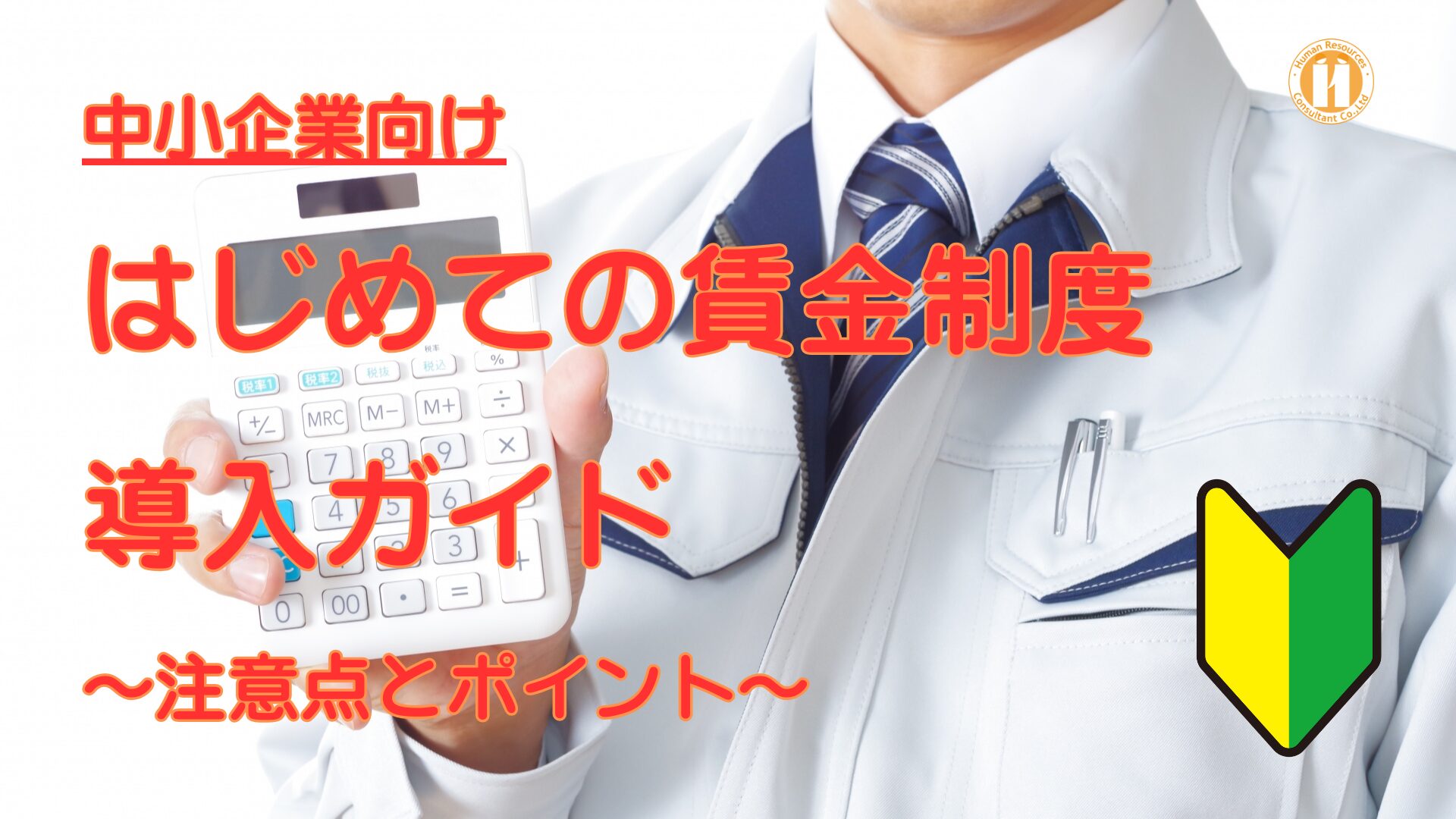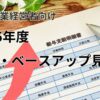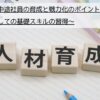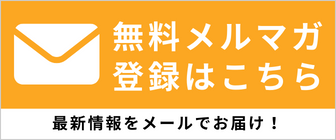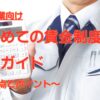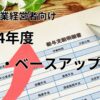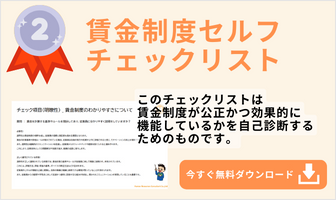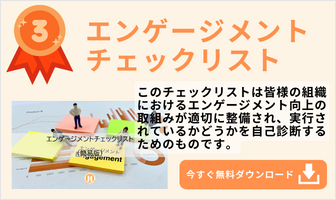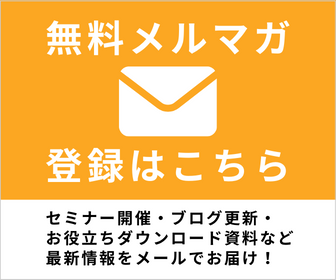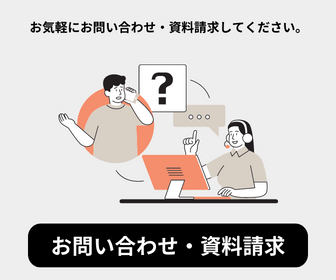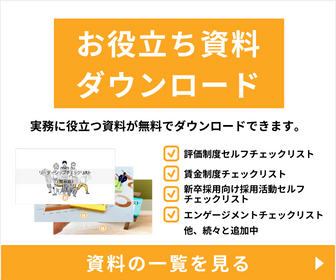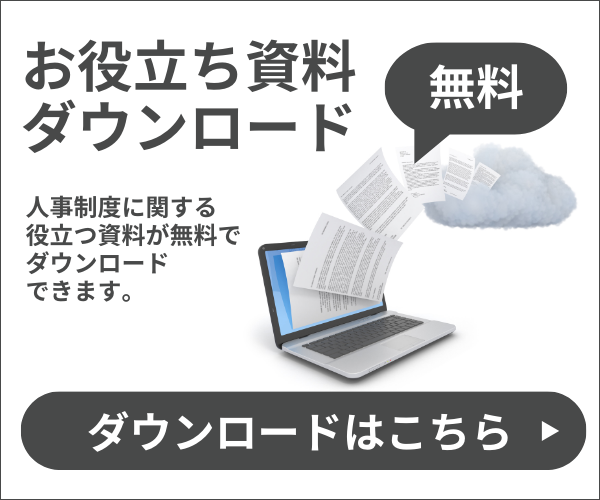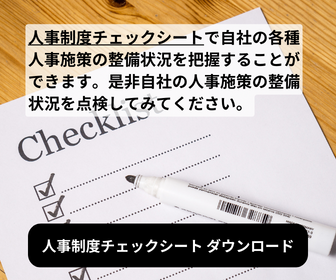中小企業向け | 2024年度春闘・ベースアップの振り返り
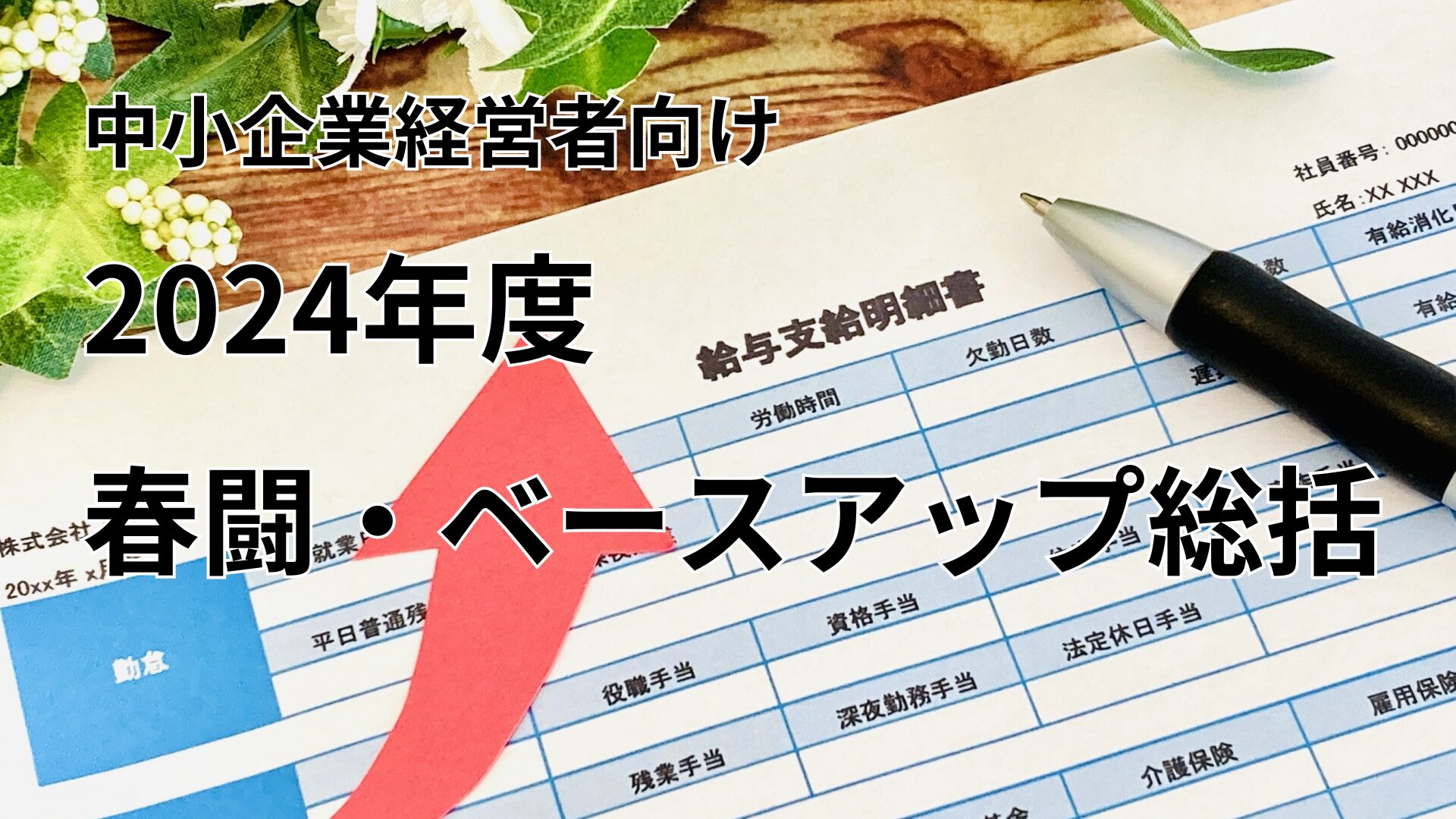
本コラムは中小企業の経営者や人事担当者の皆様に向けて、2024年の春闘の結果や傾向を総括したものです。公表データを参考にしながら、春闘全体の動向と大手企業・中小企業それぞれの賃上げ状況、さらに背景にある経済環境や今後の注目ポイントについて解説いたします。
はじめに
2024年の春闘は、コロナ禍からの回復基調が定着しつつある一方で、原材料やエネルギーコストの高騰による物価上昇が続く中で行われました。政府や日銀は賃金上昇と物価上昇の好循環を促すため、中小企業を含む幅広い業種の賃上げを推奨してきました。こうした政策支援や世間の注目の高まりもあり、2023年に引き続いて比較的高い水準の賃上げ率が期待される状況でした。
しかしながら、一方で日本企業の多くが引き続きコスト増加に頭を悩ませていることも事実です。大手企業は世界的なサプライチェーンの変動や地政学リスクの影響を受けつつも、業績回復傾向が維持されている企業も少なくありません。他方、中小企業は人手不足の深刻化に加え、円安による輸入コスト増、エネルギー価格の上昇といった負担を強いられており、「賃上げをどの程度実施できるか」について慎重な議論を進めてきました。
本稿では、大手企業と中小企業それぞれの賃上げ率や、春闘結果から見えてくる2024年の労使交渉の特徴について、公表データを交えて整理していきます。さらに、中小企業経営者の視点から、今後の賃金・人事戦略における留意点も考察していきたいと思います。
大手企業の動向
まず、大手企業の賃上げ動向を概観します。日本経団連が2024年8月に公表した「2024年春季労使交渉に関する集計結果(最終集計)」によりますと、主要企業の平均賃上げ率(ベースアップおよび定期昇給を含む総合計)は**3.9%**前後となりました(※1)。これは2023年の同時期最終集計値(約3.91%)とおおむね同水準であり、2022年以前と比べても高い水準を維持しています。
大手企業の春闘では、以下の点が特徴として挙げられます。
- インフレを意識したベースアップ
物価上昇が続く中、従業員の生活防衛を意識したベースアップ率の引き上げが継続しています。特に、自動車・電機・鉄鋼など輸出比率が高く、為替差益や海外事業の収益増が見込まれる企業では、業績拡大を反映して比較的高めの回答を示す傾向が続いています。 - 業績との連動強化
コロナ禍からの回復で売上・利益が改善した企業は賃上げに前向きな姿勢をとり、企業収益を確保しながら人材確保にも力を入れています。特にデジタル人材や研究開発職など、専門性の高い部門では人材流出を防ぐために賃上げ幅が大きくなるケースも目立っています。 - 物価上昇率との乖離
一方で、消費者物価指数(CPI)の上昇率との比較においては、企業によっては「物価上昇分を十分にカバーできているかどうか」について、従業員サイドから疑問が挙がる場面もありました。ただし、大手企業では賞与や一時金などを含めた総合的な処遇改善で対応しているところが多く、最終的には労使折り合いがついたケースが大半とみられています。
※1 参考:日本経団連「2024年春季労使交渉 最終集計結果」
中小企業の動向
続いて、中小企業の動向をみていきます。日本商工会議所が2024年6月に公表した調査結果(※2)によれば、従業員300人未満の中小企業の賃上げ率(定期昇給とベースアップの合計)は2.8%程度が平均値として示されています。2023年は2.6%前後だったとの報告があり、今年は若干ながら上昇傾向が見られますが、大手企業と比較すると依然として差がある状況です。
中小企業における春闘の主な特徴としては以下の点が挙げられます。
- 人手不足と賃上げ圧力
中小企業では、深刻化する人手不足の中で人材確保を図るために賃上げや処遇改善の必要性が高まっています。特に地域密着型の中小企業やサービス業などでは、アルバイトやパートを含めた人材不足が深刻であり、最低賃金の上昇に合わせて時給レベルの見直しも求められています。 - 原材料費・光熱費などコスト増の影響
円安やエネルギー価格の上昇によるコスト増は、中小企業にとっては依然として重い負担となっています。売上が十分に伸びない状況下で、従業員への還元をどの程度実施するかは頭を悩ませるポイントです。結果的に、大手企業ほど積極的な賃上げが難しいケースが多いとみられています。 - 行政支援策の活用
厚生労働省や中小企業庁などが打ち出す人材育成支援策や賃上げ支援策を活用し、何とか従業員の給与改善に取り組む企業も増えています。具体的には、生産性向上や業務効率化に寄与する設備投資への補助金や助成金を活用し、コスト削減によって生まれた余力を賃上げ原資に回す事例も見られます。 - 経営改善と給与水準の両立の難しさ
中小企業の場合、経営トップと従業員が顔の見える関係で協力しながら業務を進めているケースが多いことから、賃上げに対して労使双方のコミュニケーションが比較的とりやすいという面もあります。しかし実際には、資金繰りやコスト管理の観点から給与水準を大幅に引き上げることが困難であることが多く、最終的には「少しでも上げたいが、大手ほどは上げられない」という結論に落ち着く企業が少なくありません。
※2 参考:日本商工会議所「2024年春闘に関する調査結果」

政府・日銀のスタンスと賃上げの今後
賃金上昇は個人消費を押し上げると同時に、デフレ脱却や経済成長のエンジンとして期待されています。政府は引き続き「経済の好循環」を目指し、企業に対して賃上げ要請を行っています。また、日銀も金融緩和政策を続けながら、物価上昇と賃金上昇が同時に進む状況を見守っています。
とはいえ、現状では以下のような懸念も残ります。
- 物価上昇率との差
消費者物価指数(CPI)の上昇率が3〜4%程度で推移する状況が続く中、賃上げ率が物価上昇率と拮抗もしくは下回ると、実質賃金が伸び悩む可能性があります。実質賃金の減少は個人消費を冷やし、景気後退リスクを高める恐れがあるため、政府としては賃上げ率のさらなる向上を期待していると言えます。 - 業種・地域間格差
コロナ禍の影響が長期化し、業種や地域による回復の差が明確化しています。観光業や外食産業など人流回復に伴い需要が戻る業種は、売上改善に合わせて賃上げしやすい環境が整いつつありますが、依然として厳しい状況にある業種もあります。中小企業についても同様に、地域によってはインバウンド需要で好調なところがある一方、地元需要が伸び悩む地域では賃上げ余力が限られるという実態も見られます。 - グローバル競争と人材獲得競争
大手企業やベンチャー企業を中心に、デジタル技術やAI人材などの高度専門人材を獲得するための競争が激化しています。人材争奪戦の影響は中小企業にも及び、給与面で太刀打ちできない場合は優秀な人材を確保できないリスクが高まります。こうした背景も、中小企業が少しでも賃上げする必要性を高める要因となっています。
中小企業が今後取るべき対応策
2024年の春闘で示された傾向を踏まえ、中小企業が今後の賃金・人事戦略を検討する際に考慮すべきポイントを以下にまとめます。
生産性向上と賃上げの両輪での取り組み
企業が従業員に十分な賃上げを行うためには、まず利益を増やす必要があります。そのための取り組みとして、生産性向上に向けた業務改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が挙げられます。国や自治体が提供する補助金や助成金を積極的に活用し、短期的なコスト負担を軽減しながら持続的な利益体質へ移行することが重要です。
給与以外の魅力づくり
賃上げが思うように進められない場合は、福利厚生や働き方改革などの「給与以外の魅力」で人材を惹きつける工夫も不可欠です。具体的には、リモートワークやフレックスタイム制の導入、有給休暇の取得推進、研修制度や資格取得支援などの制度拡充が挙げられます。大手企業にはない温かみや柔軟性をアピールできれば、中小企業ならではの採用力を高めることができます。
エンゲージメントと企業文化の醸成
中小企業では、従業員一人ひとりの役割が大きく、企業の成長に直接貢献している実感を得やすい環境でもあります。単に給与を上げるだけでなく、経営者がビジョンや方針を明確にし、従業員と共有することで、組織全体の結束力とエンゲージメントを高めることが重要です。エンゲージメントが高まれば、従業員は自社への誇りをもって働くようになり、生産性向上や顧客満足度向上に直結しやすくなります。
段階的かつ計画的な賃上げ
一度に大幅な賃上げは難しくても、「今後3〜5年で総額人件費をどの程度上げていくか」という中長期的な計画を示すだけでも、従業員の安心感やモチベーション向上につながります。賞与や一時金を見直して業績との連動性を高めるなど、企業の経営状況に合わせて段階的に改善を進める姿勢を示すことが大切です。
まとめ:2024年春闘から見える中小企業の課題と展望
2024年の春闘は、大手企業と中小企業のいずれも「賃上げ率」が2023年に引き続き比較的高めの水準で推移したものの、大手は**3.9%前後、中小企業は2.8%**程度と依然として開きがある結果となりました。背景には、人材確保の必要性が高まる一方で、原材料費や光熱費などのコスト増が業績を圧迫している構造的な問題が存在します。
また、政府・日銀は物価上昇と賃金上昇の好循環を促しており、今後も企業に対して賃上げ努力が求められることが予想されます。しかし、中小企業が十分な賃上げを行うためには、業務の効率化や新しい技術・サービスへの挑戦、さらには補助金・助成金を活用した投資など、生産性向上と利益拡大に向けた施策を継続的に進めていく必要があります。
経営者や人事担当者の皆様におかれましては、短期的なコスト増にとらわれすぎず、将来的な企業価値の向上と人材確保・定着を両立させるビジョンを持つことが重要です。給与や待遇の改善はもちろん、職場環境・働き方改革、企業文化の確立など、社員が長期的に安心して働ける施策の総合的な見直しが求められます。
2024年の春闘が示す大手企業の高い賃上げ率は、国内外での人材獲得競争がさらに激化していることを反映しています。中小企業は大手と同じ賃上げを実現することは容易ではありませんが、「魅力のある企業づくり」という観点を持って戦略的に取り組むことが、今後の生き残りと発展のカギとなるでしょう。今後も社会情勢や経済環境が変化していく中で、労使の対話を密に行いながら、企業の状況に即した柔軟な対応策を講じていただければと思います。
本稿が、皆様の経営や人事戦略を再考する際の一助となれば幸いです。2024年春闘の結果を踏まえ、引き続き中小企業ならではの強みを活かしつつ、人材を支え、育て、企業と従業員がともに成長できる環境を整えていきましょう。
以上が2024年春闘の結果・傾向の総括となります。厳しい経営環境が続く中での賃上げ実施は容易ではありませんが、今後の日本経済全体の成長を支えるためにも、一歩踏み込んだ労使交渉と戦略的な経営判断が求められています。中小企業の皆様には、こうした難局を逆にチャンスと捉え、イノベーションや組織力強化に注力しながら、持続的な成長につなげていただければと願っております。
投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。
最新の投稿
 コラム2025年4月2日中小企業向け | はじめて退職金制度を導入するときの注意点とポイント
コラム2025年4月2日中小企業向け | はじめて退職金制度を導入するときの注意点とポイント コラム2025年4月2日中小企業向け | はじめて賃金制度を導入するときの注意点とポイント
コラム2025年4月2日中小企業向け | はじめて賃金制度を導入するときの注意点とポイント コラム2025年4月2日中小企業向け | はじめて人事評価制度を導入するときの注意点とポイント
コラム2025年4月2日中小企業向け | はじめて人事評価制度を導入するときの注意点とポイント コラム2025年3月27日中小企業向け | 2024年度春闘・ベースアップの振り返り
コラム2025年3月27日中小企業向け | 2024年度春闘・ベースアップの振り返り